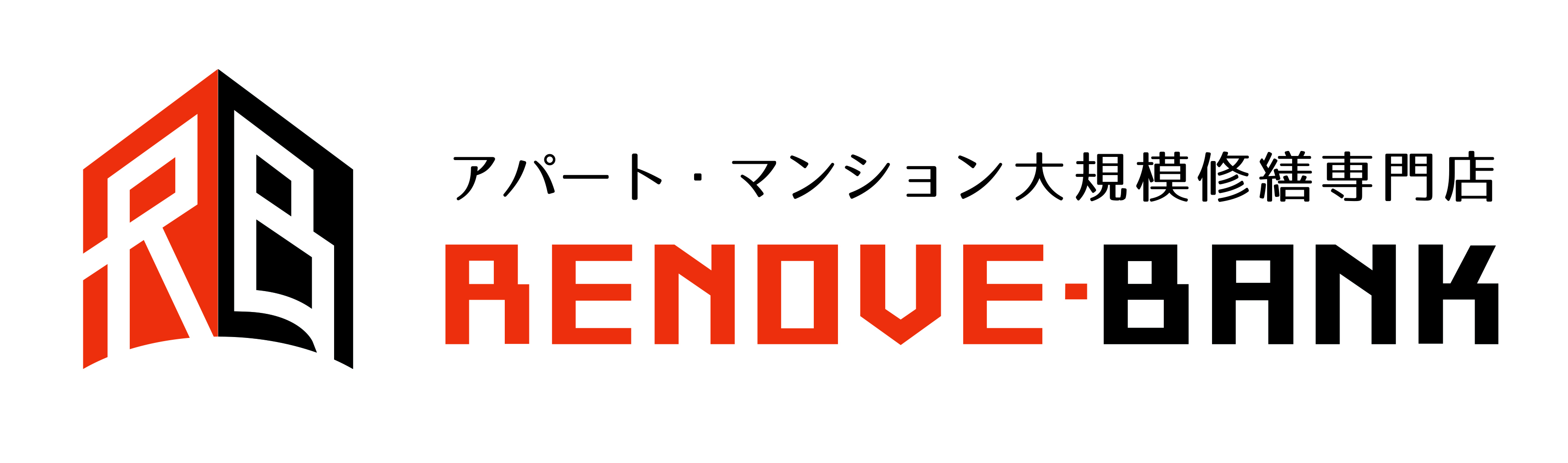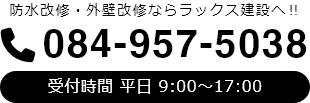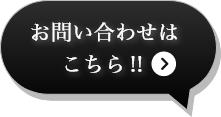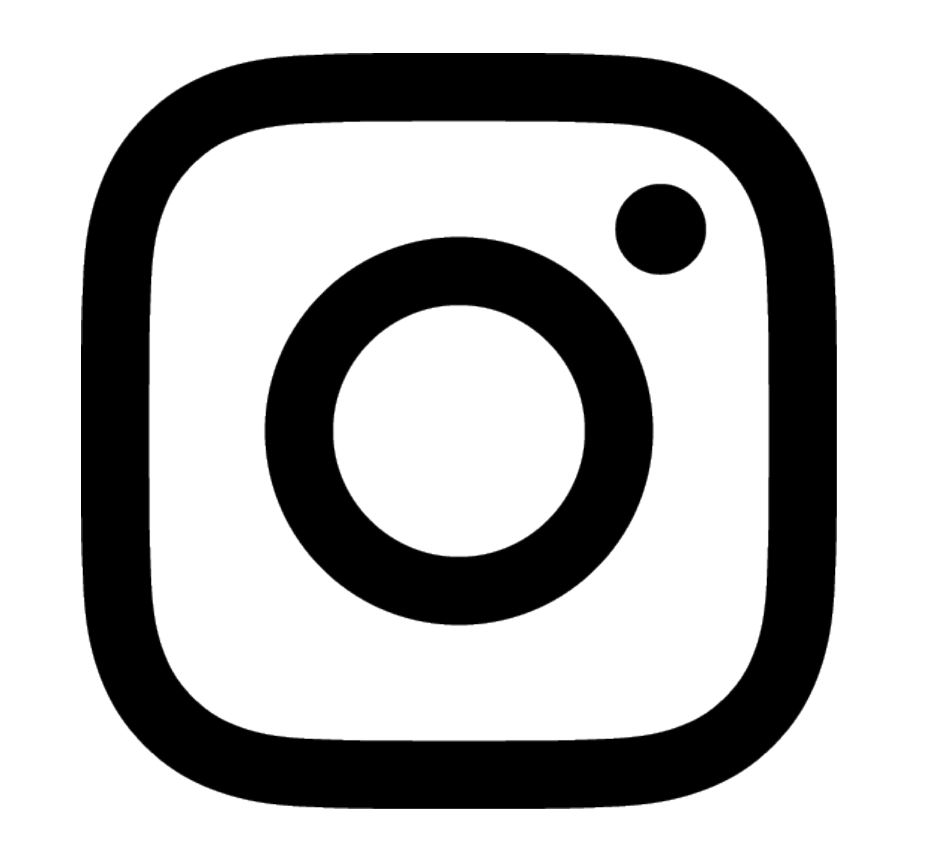2025年05月28日
一)職業にはいろんな種類があると思うが、大きく分けて職人と商人と公人の三つだと思う。職人とは技能職、商人とは営業職、公人とは公務員や議員のこと。うちは建設業だから職人ではあるけれど、お客様がいる限り商人でもある。
二)私はお客様からお金や報酬を頂く職業であれば、すべて商人だと思う。ビジネスというのは販売先と仕入先があるわけで、病院も患者がお客様(販売先)であり製薬メーカーは仕入先、宗教も信者がお客様で出版会社などが仕入先だろう。販売先がないのは公人だけだ。
三)私の好きな言葉に『士魂商才』というものがある。武士の精神と商人としての抜け目ない才能とを併せもっているという意味だが、この度は、この商人について書かれてある『伊藤忠 商人の心得(野地秩嘉著/新潮新書)』という本を読んでメモした言葉をここで一部紹介したい。※印は私の勝手な所感。
四)P4:商人とは業種で決まるわけではなく、つねづね客と接し、客が欲しいものを作る人、客が望むものを探して持ってくる人を言う。※私も全く同じ考え。売り先、販売先のある職業はすべて商売だし、それを担うのが商人だ。
五)P13:「か・け・ふ」とは伊藤忠が実行するべき商いの三原則で、稼ぐ・削る・防ぐの頭文字を取ったもの。※なるほど、とても分かりやすい。うちの業界に当てはめると、できる限り早く工事を終わらせ、コストを下げて、ミスや災害を防ぐということ。
六)P40:会社にとって本当の客は誰か。もしかすると、本当のお客さんは、目の前の相手ではない場合がある。※これは例えばうちの場合だと交渉している相手がその会社の購買担当の方であっても、選択や意思決定をするのは製造担当の方であったりするということ。つまり製造担当者のニーズを汲み取れということ。
七)P44:商売では自分以外の誰かのために働くのがいちばん力が出る。自分のためよりも弱い者の味方。力のなかった者のために微力を尽くすのが商人。※他の本にも「人は他人に尽くすことで自分の力を量ることができる」という言葉があった。商売に限らず、どんな仕事もそういうものだと思う。
八)P66:地位や肩書がある人間ほど手土産、プレゼントを真剣に検討しているのである。(中略)手土産ひとつでシーンを変えることができるとわかっているのが本当の商人だ。※私は全く出来ていない。基本、買い物が苦手な私はそのあたりが無頓着だから心掛けたい。
九)P141:契約を結んだとしても、リスクを感じたら撤退する。その場合、補償しなくてもいいように契約の条項を精査する。※これも私は全く出来ていない。そもそも撤退するのが下手な性分で、ついついしぶとく続けてしまう。これも気を付けたい(苦笑)。
十)P177:部下の報告をそのまま聞いて判断しているようでは生きた経営は出来ない。※この言葉も、とても耳が痛い。報告だけを頼りにしていると判断を誤る。誤るとついその部下に腹を立ててしまう。報告を鵜吞みにせずに自分の目でも確かめることが大切だということ。
二)私はお客様からお金や報酬を頂く職業であれば、すべて商人だと思う。ビジネスというのは販売先と仕入先があるわけで、病院も患者がお客様(販売先)であり製薬メーカーは仕入先、宗教も信者がお客様で出版会社などが仕入先だろう。販売先がないのは公人だけだ。
三)私の好きな言葉に『士魂商才』というものがある。武士の精神と商人としての抜け目ない才能とを併せもっているという意味だが、この度は、この商人について書かれてある『伊藤忠 商人の心得(野地秩嘉著/新潮新書)』という本を読んでメモした言葉をここで一部紹介したい。※印は私の勝手な所感。
四)P4:商人とは業種で決まるわけではなく、つねづね客と接し、客が欲しいものを作る人、客が望むものを探して持ってくる人を言う。※私も全く同じ考え。売り先、販売先のある職業はすべて商売だし、それを担うのが商人だ。
五)P13:「か・け・ふ」とは伊藤忠が実行するべき商いの三原則で、稼ぐ・削る・防ぐの頭文字を取ったもの。※なるほど、とても分かりやすい。うちの業界に当てはめると、できる限り早く工事を終わらせ、コストを下げて、ミスや災害を防ぐということ。
六)P40:会社にとって本当の客は誰か。もしかすると、本当のお客さんは、目の前の相手ではない場合がある。※これは例えばうちの場合だと交渉している相手がその会社の購買担当の方であっても、選択や意思決定をするのは製造担当の方であったりするということ。つまり製造担当者のニーズを汲み取れということ。
七)P44:商売では自分以外の誰かのために働くのがいちばん力が出る。自分のためよりも弱い者の味方。力のなかった者のために微力を尽くすのが商人。※他の本にも「人は他人に尽くすことで自分の力を量ることができる」という言葉があった。商売に限らず、どんな仕事もそういうものだと思う。
八)P66:地位や肩書がある人間ほど手土産、プレゼントを真剣に検討しているのである。(中略)手土産ひとつでシーンを変えることができるとわかっているのが本当の商人だ。※私は全く出来ていない。基本、買い物が苦手な私はそのあたりが無頓着だから心掛けたい。
九)P141:契約を結んだとしても、リスクを感じたら撤退する。その場合、補償しなくてもいいように契約の条項を精査する。※これも私は全く出来ていない。そもそも撤退するのが下手な性分で、ついついしぶとく続けてしまう。これも気を付けたい(苦笑)。
十)P177:部下の報告をそのまま聞いて判断しているようでは生きた経営は出来ない。※この言葉も、とても耳が痛い。報告だけを頼りにしていると判断を誤る。誤るとついその部下に腹を立ててしまう。報告を鵜吞みにせずに自分の目でも確かめることが大切だということ。
コメント (0) |トラックバック (0)
トラックバックURL : ボットからトラックバックURLを保護しています