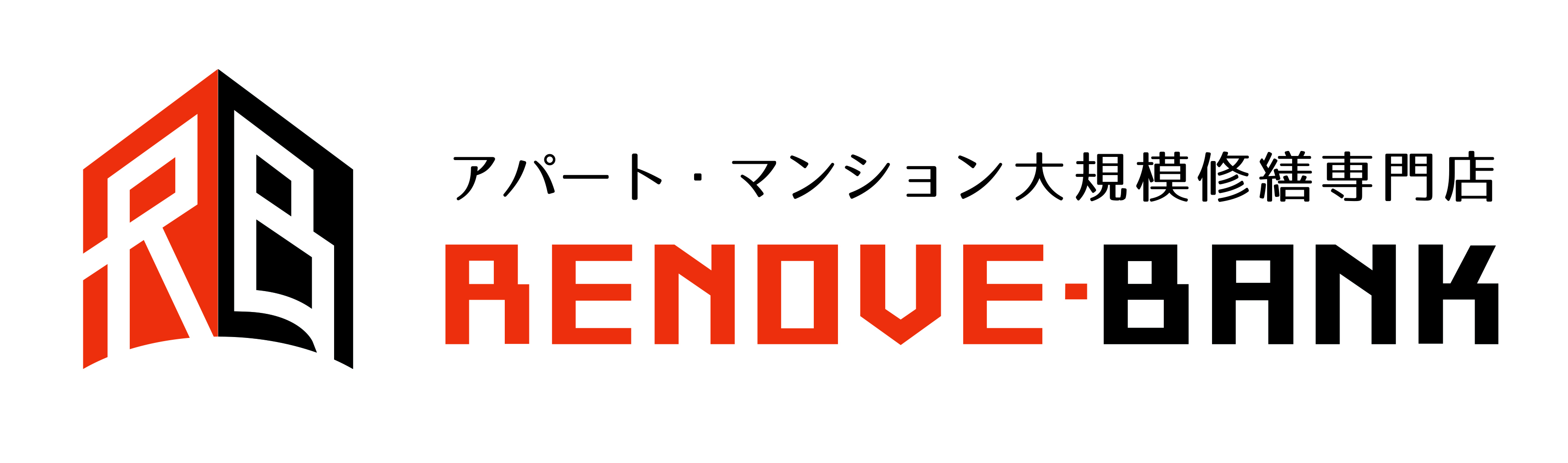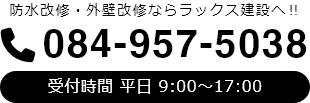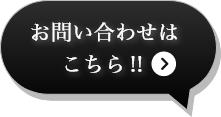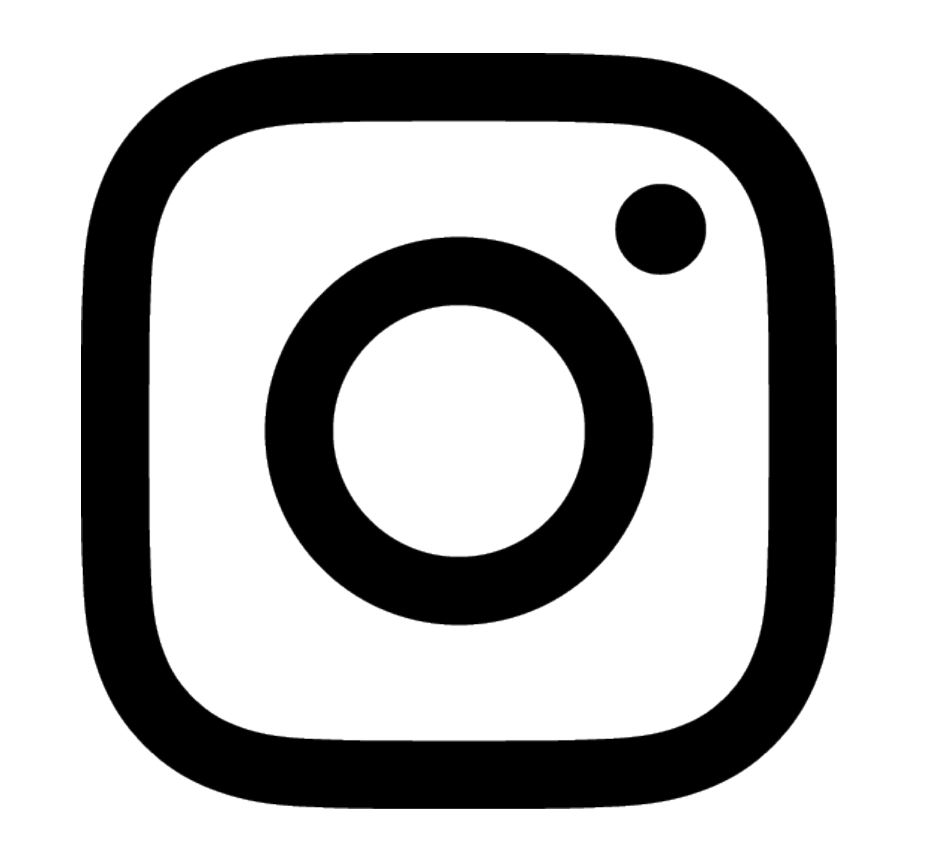2025年07月16日
(一)仕事に感情を持ち込むのは禁物だ。それは感情的な言動や感情的な判断や意思決定、気分の良し悪しでやったりやらなかったりすることだ。特に役職や立場が高くなればなるほど、感情的な言動や判断は業務に対するインパクトが大きいので慎むべきだ。
(二)感情的なことをポジティブに言えば「素直」とか「正直」というのだろうが、ネガティブに言えば「大人気ない」し「幼稚」で「危なっかしい」というところだろう。傷害や殺人などの犯罪は、そのほとんどが感情的で衝動的な行為の結果だ。
(三)そもそも仕事とは、個人的な感情や気分に全く関係なく、目的や目標に向かい方針に沿って計画通りに進めるべきものであり、常にお客様の課題解決に努めるのがビジネスのはず。個人の感情の起伏で、結果や成果が上がったり下がったりするべきではない。
(四)仕事の中で感情的な言動や判断が、いろんな場面で弊害をもたらす。たとえば、上司と部下の関係で、上司の方がその時の気分の良し悪しや相性の合う合わないで、部下に対して言葉少なげに投げやりな指示をしたり、逆に機嫌よく無駄に余計な時間を使って回りくどくおせっかいをしたり。
(五)反対に部下の方も、自分の好き嫌いで上司の言う事を聞いたり聞かなかったり、報告したりしなかったり。こうなると業務や指示で分からないことがあっても、相談もせずに遂行してしまうからポカやミスが発生する。ここまでくると、人間関係よりもその人の責任感を疑ってしまう。
(六)上司と部下の関係は、指示する側と指示される側、教える側と教えられる側、育てる側と育てられる側、助ける側と助けられる側という具合に、あくまで業務を遂行する上で、一番効率的で効果的な関係でなければならない。それが組織であり会社なのだ。そこに個人的な感情を入れる余地はない。
(七)当然、生身の人間なので、誰でも好き嫌いもあれば、気分の浮き沈みもあるし、その時の体調の良し悪しもある。ただ、仕事もスポーツも同じだと思うが、チームワークと好き嫌いは関係ない。好き嫌いなどはプライベートで付き合いをはっきりさせればいい。チームワークとはそんなの関係なしに勝つためにみんなで力を合わせることだ。
(八)内部だけならまだいいが、外部に対して感情的な言動や意思決定をすることは、もはや会社の信用や業績に大きな支障をきたす問題行動だ。そうなってくると厳しい指導か配置転換、それでも改善できなければ会社を守るために降級
(九)そこで、いかに感情的な言動や判断を抑えるか。私が思うには次の三つの習慣が効果あると思う。少なくとも短気、単純、単細胞だった私が少しは改善できたと思っている。それは「読書」「瞑想」「運動」だ。まず読書は、いろんな本をたくさん読んで知識や語彙力を高めれば、頭の中で論理的に冷静に考えられるようになる。
(十)瞑想は、姿勢を正し、目を閉じて呼吸を整えることで平常心と理性を養える。そして最後に適度な運動は、健全な精神は健全な肉体に宿ると言われている通り、やはり健康でないと、よっぽど強い精神力でない限り感傷的な領域から抜け出せないだろう。感情的な言動や判断を抑えるために、ぜひ「読書」「瞑想」「運動」を薦めたい。
(二)感情的なことをポジティブに言えば「素直」とか「正直」というのだろうが、ネガティブに言えば「大人気ない」し「幼稚」で「危なっかしい」というところだろう。傷害や殺人などの犯罪は、そのほとんどが感情的で衝動的な行為の結果だ。
(三)そもそも仕事とは、個人的な感情や気分に全く関係なく、目的や目標に向かい方針に沿って計画通りに進めるべきものであり、常にお客様の課題解決に努めるのがビジネスのはず。個人の感情の起伏で、結果や成果が上がったり下がったりするべきではない。
(四)仕事の中で感情的な言動や判断が、いろんな場面で弊害をもたらす。たとえば、上司と部下の関係で、上司の方がその時の気分の良し悪しや相性の合う合わないで、部下に対して言葉少なげに投げやりな指示をしたり、逆に機嫌よく無駄に余計な時間を使って回りくどくおせっかいをしたり。
(五)反対に部下の方も、自分の好き嫌いで上司の言う事を聞いたり聞かなかったり、報告したりしなかったり。こうなると業務や指示で分からないことがあっても、相談もせずに遂行してしまうからポカやミスが発生する。ここまでくると、人間関係よりもその人の責任感を疑ってしまう。
(六)上司と部下の関係は、指示する側と指示される側、教える側と教えられる側、育てる側と育てられる側、助ける側と助けられる側という具合に、あくまで業務を遂行する上で、一番効率的で効果的な関係でなければならない。それが組織であり会社なのだ。そこに個人的な感情を入れる余地はない。
(七)当然、生身の人間なので、誰でも好き嫌いもあれば、気分の浮き沈みもあるし、その時の体調の良し悪しもある。ただ、仕事もスポーツも同じだと思うが、チームワークと好き嫌いは関係ない。好き嫌いなどはプライベートで付き合いをはっきりさせればいい。チームワークとはそんなの関係なしに勝つためにみんなで力を合わせることだ。
(八)内部だけならまだいいが、外部に対して感情的な言動や意思決定をすることは、もはや会社の信用や業績に大きな支障をきたす問題行動だ。そうなってくると厳しい指導か配置転換、それでも改善できなければ会社を守るために降級
(九)そこで、いかに感情的な言動や判断を抑えるか。私が思うには次の三つの習慣が効果あると思う。少なくとも短気、単純、単細胞だった私が少しは改善できたと思っている。それは「読書」「瞑想」「運動」だ。まず読書は、いろんな本をたくさん読んで知識や語彙力を高めれば、頭の中で論理的に冷静に考えられるようになる。
(十)瞑想は、姿勢を正し、目を閉じて呼吸を整えることで平常心と理性を養える。そして最後に適度な運動は、健全な精神は健全な肉体に宿ると言われている通り、やはり健康でないと、よっぽど強い精神力でない限り感傷的な領域から抜け出せないだろう。感情的な言動や判断を抑えるために、ぜひ「読書」「瞑想」「運動」を薦めたい。
コメント (0) |トラックバック (0)
トラックバックURL : ボットからトラックバックURLを保護しています
2025年06月18日
一)経営について勉強したり、戦略について議論したりするときに、安く売ることは誰でも出来るし、安易で短絡的で能力の低い選択のように言われることが多いが、私は決してそうとは思わない。確かに、一円でも高く売ることができるのは能力かもしれないが、継続できないと全く意味がない。
二)高く売れれば、その分だけ儲けも増えるが、そこに高く売れる付加価値がなければ、単なるぼったくりか、たまたま偶然タイミングがよかったか、買い手の目が節穴だったいうことになる。どちらにせよ長く続くわけがない。
三)そういう点において、仕入れや加工、仕組みや社員教育を工夫して、計画的に安定した収益が得られるのであれば、安く売るというのは「三方善し」の立派な戦略だし賢い経営だと思う。でもそれは高く売るよりも、もっと難易度が高い戦略だ。
四)そこで、イタリア料理を他社が追従できないくらい超低価格で提供しながら成長しているサイゼリヤの創業者が書いた本『サイゼリヤ おいしいから売れるのではない 売れるのがおいしい料理だ(正垣泰彦著/日本経済新聞出版社)』を読んでみた。私がノートに書き留めた一部の言葉を紹介したい。※印は私の勝手な所感。
五)P22:絞り込んでメニューを提供すると食材ロスが減り、作業効率も良くなる。無駄を省くので利益もドンドン出る。(中略)無駄をそぎ落とすことでお値打ちな商品になるからお客様に喜ばれて売り上げも最終的に増えるので、初めに安売りありきではないのだ。※凡人は先に安売りしてしまう。
六)P60:適正な利益を確保するという意味で、私が創業時から重視する経営指標が「人時生産性」だ。「人時生産性」とは1日に生じた店舗の粗利益を、その日に働いていた従業員全員の総労働時間で割ったものだ。※ここで大切なのは分子が売上ではなく粗利益ということ。うちも同じ指標を重視している。
七)P70:瓶ビール1本とか玉ねぎ1個あたり数円安く仕入れても、削れるコストは知れている。そんなことに頭を使うよりは「今、2人で行っている作業を何とか1人でできないか」など最大のコストである人件費を削ることを考えるほうがよっぽど生産的だ。※建設業も同じことが言えるが職人気質はこれを避ける傾向がある。
八)P77:コスト削減というと、ある支出の中からムダを見つけて、それを減らしていくというパターンが多いが、それよりも支出額を決めて、それ以上は絶対に使わないようにした方がコスト削減は進む。※つまり予実管理を徹底しろということ。私が一番苦手とするところだ(苦笑)。
九)P112:「この人、急に変になったの」と心配されるくらいに大きな目標を持つのが、ちょうどよいと思う。そうすれば、自分より優秀な人材が、あなたや仲間の夢をかなえるために力を貸してくれるはずだ。※私は目標は現実的な外向きの目標と挑戦的な内向きの2つの目標があった方がいいと思う。
十)他にもたくさん紹介したいが、ぜひ原本の購読をすすめる。多くの経験則から裏付けられた原理原則や指標が、惜しみなくたくさん述べられており、とても勉強になる。安く売って儲け続けるには高い能力が求められるのだ。
二)高く売れれば、その分だけ儲けも増えるが、そこに高く売れる付加価値がなければ、単なるぼったくりか、たまたま偶然タイミングがよかったか、買い手の目が節穴だったいうことになる。どちらにせよ長く続くわけがない。
三)そういう点において、仕入れや加工、仕組みや社員教育を工夫して、計画的に安定した収益が得られるのであれば、安く売るというのは「三方善し」の立派な戦略だし賢い経営だと思う。でもそれは高く売るよりも、もっと難易度が高い戦略だ。
四)そこで、イタリア料理を他社が追従できないくらい超低価格で提供しながら成長しているサイゼリヤの創業者が書いた本『サイゼリヤ おいしいから売れるのではない 売れるのがおいしい料理だ(正垣泰彦著/日本経済新聞出版社)』を読んでみた。私がノートに書き留めた一部の言葉を紹介したい。※印は私の勝手な所感。
五)P22:絞り込んでメニューを提供すると食材ロスが減り、作業効率も良くなる。無駄を省くので利益もドンドン出る。(中略)無駄をそぎ落とすことでお値打ちな商品になるからお客様に喜ばれて売り上げも最終的に増えるので、初めに安売りありきではないのだ。※凡人は先に安売りしてしまう。
六)P60:適正な利益を確保するという意味で、私が創業時から重視する経営指標が「人時生産性」だ。「人時生産性」とは1日に生じた店舗の粗利益を、その日に働いていた従業員全員の総労働時間で割ったものだ。※ここで大切なのは分子が売上ではなく粗利益ということ。うちも同じ指標を重視している。
七)P70:瓶ビール1本とか玉ねぎ1個あたり数円安く仕入れても、削れるコストは知れている。そんなことに頭を使うよりは「今、2人で行っている作業を何とか1人でできないか」など最大のコストである人件費を削ることを考えるほうがよっぽど生産的だ。※建設業も同じことが言えるが職人気質はこれを避ける傾向がある。
八)P77:コスト削減というと、ある支出の中からムダを見つけて、それを減らしていくというパターンが多いが、それよりも支出額を決めて、それ以上は絶対に使わないようにした方がコスト削減は進む。※つまり予実管理を徹底しろということ。私が一番苦手とするところだ(苦笑)。
九)P112:「この人、急に変になったの」と心配されるくらいに大きな目標を持つのが、ちょうどよいと思う。そうすれば、自分より優秀な人材が、あなたや仲間の夢をかなえるために力を貸してくれるはずだ。※私は目標は現実的な外向きの目標と挑戦的な内向きの2つの目標があった方がいいと思う。
十)他にもたくさん紹介したいが、ぜひ原本の購読をすすめる。多くの経験則から裏付けられた原理原則や指標が、惜しみなくたくさん述べられており、とても勉強になる。安く売って儲け続けるには高い能力が求められるのだ。
コメント (0) |トラックバック (0)
トラックバックURL : ボットからトラックバックURLを保護しています
2025年05月28日
一)職業にはいろんな種類があると思うが、大きく分けて職人と商人と公人の三つだと思う。職人とは技能職、商人とは営業職、公人とは公務員や議員のこと。うちは建設業だから職人ではあるけれど、お客様がいる限り商人でもある。
二)私はお客様からお金や報酬を頂く職業であれば、すべて商人だと思う。ビジネスというのは販売先と仕入先があるわけで、病院も患者がお客様(販売先)であり製薬メーカーは仕入先、宗教も信者がお客様で出版会社などが仕入先だろう。販売先がないのは公人だけだ。
三)私の好きな言葉に『士魂商才』というものがある。武士の精神と商人としての抜け目ない才能とを併せもっているという意味だが、この度は、この商人について書かれてある『伊藤忠 商人の心得(野地秩嘉著/新潮新書)』という本を読んでメモした言葉をここで一部紹介したい。※印は私の勝手な所感。
四)P4:商人とは業種で決まるわけではなく、つねづね客と接し、客が欲しいものを作る人、客が望むものを探して持ってくる人を言う。※私も全く同じ考え。売り先、販売先のある職業はすべて商売だし、それを担うのが商人だ。
五)P13:「か・け・ふ」とは伊藤忠が実行するべき商いの三原則で、稼ぐ・削る・防ぐの頭文字を取ったもの。※なるほど、とても分かりやすい。うちの業界に当てはめると、できる限り早く工事を終わらせ、コストを下げて、ミスや災害を防ぐということ。
六)P40:会社にとって本当の客は誰か。もしかすると、本当のお客さんは、目の前の相手ではない場合がある。※これは例えばうちの場合だと交渉している相手がその会社の購買担当の方であっても、選択や意思決定をするのは製造担当の方であったりするということ。つまり製造担当者のニーズを汲み取れということ。
七)P44:商売では自分以外の誰かのために働くのがいちばん力が出る。自分のためよりも弱い者の味方。力のなかった者のために微力を尽くすのが商人。※他の本にも「人は他人に尽くすことで自分の力を量ることができる」という言葉があった。商売に限らず、どんな仕事もそういうものだと思う。
八)P66:地位や肩書がある人間ほど手土産、プレゼントを真剣に検討しているのである。(中略)手土産ひとつでシーンを変えることができるとわかっているのが本当の商人だ。※私は全く出来ていない。基本、買い物が苦手な私はそのあたりが無頓着だから心掛けたい。
九)P141:契約を結んだとしても、リスクを感じたら撤退する。その場合、補償しなくてもいいように契約の条項を精査する。※これも私は全く出来ていない。そもそも撤退するのが下手な性分で、ついついしぶとく続けてしまう。これも気を付けたい(苦笑)。
十)P177:部下の報告をそのまま聞いて判断しているようでは生きた経営は出来ない。※この言葉も、とても耳が痛い。報告だけを頼りにしていると判断を誤る。誤るとついその部下に腹を立ててしまう。報告を鵜吞みにせずに自分の目でも確かめることが大切だということ。
二)私はお客様からお金や報酬を頂く職業であれば、すべて商人だと思う。ビジネスというのは販売先と仕入先があるわけで、病院も患者がお客様(販売先)であり製薬メーカーは仕入先、宗教も信者がお客様で出版会社などが仕入先だろう。販売先がないのは公人だけだ。
三)私の好きな言葉に『士魂商才』というものがある。武士の精神と商人としての抜け目ない才能とを併せもっているという意味だが、この度は、この商人について書かれてある『伊藤忠 商人の心得(野地秩嘉著/新潮新書)』という本を読んでメモした言葉をここで一部紹介したい。※印は私の勝手な所感。
四)P4:商人とは業種で決まるわけではなく、つねづね客と接し、客が欲しいものを作る人、客が望むものを探して持ってくる人を言う。※私も全く同じ考え。売り先、販売先のある職業はすべて商売だし、それを担うのが商人だ。
五)P13:「か・け・ふ」とは伊藤忠が実行するべき商いの三原則で、稼ぐ・削る・防ぐの頭文字を取ったもの。※なるほど、とても分かりやすい。うちの業界に当てはめると、できる限り早く工事を終わらせ、コストを下げて、ミスや災害を防ぐということ。
六)P40:会社にとって本当の客は誰か。もしかすると、本当のお客さんは、目の前の相手ではない場合がある。※これは例えばうちの場合だと交渉している相手がその会社の購買担当の方であっても、選択や意思決定をするのは製造担当の方であったりするということ。つまり製造担当者のニーズを汲み取れということ。
七)P44:商売では自分以外の誰かのために働くのがいちばん力が出る。自分のためよりも弱い者の味方。力のなかった者のために微力を尽くすのが商人。※他の本にも「人は他人に尽くすことで自分の力を量ることができる」という言葉があった。商売に限らず、どんな仕事もそういうものだと思う。
八)P66:地位や肩書がある人間ほど手土産、プレゼントを真剣に検討しているのである。(中略)手土産ひとつでシーンを変えることができるとわかっているのが本当の商人だ。※私は全く出来ていない。基本、買い物が苦手な私はそのあたりが無頓着だから心掛けたい。
九)P141:契約を結んだとしても、リスクを感じたら撤退する。その場合、補償しなくてもいいように契約の条項を精査する。※これも私は全く出来ていない。そもそも撤退するのが下手な性分で、ついついしぶとく続けてしまう。これも気を付けたい(苦笑)。
十)P177:部下の報告をそのまま聞いて判断しているようでは生きた経営は出来ない。※この言葉も、とても耳が痛い。報告だけを頼りにしていると判断を誤る。誤るとついその部下に腹を立ててしまう。報告を鵜吞みにせずに自分の目でも確かめることが大切だということ。
コメント (0) |トラックバック (0)
トラックバックURL : ボットからトラックバックURLを保護しています
2025年05月07日
一)一般的にプリンシプルとは日本語で「原理原則」や「主義」と訳される。このプリンシプルを戦中戦後に貫きGHQに「従順ならざる唯一の日本人」と言わしめた白洲次郎氏に関する本『白洲次郎100の言葉(別冊宝島編集部)』を読んで感銘を受けた言葉の一部をここに紹介したい。※印は私の勝手な所感。
二)P8:「我々は戦争には負けたが奴隷になったのではない」※当時、敗戦国となった日本にこの気概を持てた日本人が何人いたんだろうか。白洲次郎氏は武士道と騎士道を併せ持ったような人で、今こそこういう気概が必要だと思う。いつまで敗戦国であり続ける必要はない。
三)P15:「弱い奴が強い奴に抑えつけられるのは世の常で致し方なしとしても、言うことだけは堂々と正しいことを言うべきだ」※これは仕事や会社でも同じで、たとえ取引額が大きい客先であっても、理不尽で倫理観に反する要求に対しては、はっきりとお断りするということ。
四)P28:「ようやく戦勝国と対等の立場になれる会議で、その晴れの日の原稿を、相手の承諾を得て相手国の言葉で書く奴がどこにいるんだ!」※これはサンフランシスコ講和条約で首席全権として吉田茂が行う演説の原稿を作った外務省に対する白洲次郎氏の言葉。これは、たとえ負けても日本人としての誇りを持つことの大切さを意味している。
五)P48:「人様に、叱られたり、とやかく言われたくらいで、引っ込む心臓は持ち合わせていない」※SNSやネットが猛威を振るっている昨今、ついつい批判や中傷、軽蔑されることを気にして言いたいことややりたいことを我慢してしまう。白洲次郎氏のような心臓を持ちたい。
六)P58:「困ったときだけ大変だ大変だと大騒ぎして、政府に泣きついてくるが、それで儲かったときは知らぬ顔の半兵衛を決め込む。プリンシプルもなく、走り出したバスに飛び乗るのがうまいだけだ」※これはある種の財界人に対する言葉らしいが、税金を払いたがらないのに助成金や補助金をたかる経営者も同じだ。
七)P60:「人に好かれようと思って仕事をするな。むしろ半分の人間に積極的に嫌われるように努力しないとちゃんとした仕事はできねえぞ」※白洲次郎氏は「リーダーなるべき人間は好かれたら終わり。7割の人間に煙たがられなければ本物ではない」とも言っている。本当にそう思う。経営者は特に。
八)P66:「地位が上がるほど役得ではなく“役損”が増えることを覚えておけ」※こんなことを現代で言うとブラックとかパワハラとか言われそうだが、昔から「ノブレス・オブリージュ」という言葉もある。「位高きは徳高きを要す」という意味だ。
九)P100:「自分より目下と思われる人間には親切にしろよ」※白洲次郎氏は「人が困っているときは助けるもんだ」とも言っている。両方とも当たり前のことだが、実際にいつでもどこでもちゃんと100%出来ているかどうか振り返ると自信がない。肝に銘じておきたい。
十)P152:「本当の友情は腹を割り合った仲にのみ生まれる。相手が好きそうなことばかり言って一時的に相手を喜ばして、してやったりと思っているなど浅はかな極みである」※全くその通り。付け加えると相手が腹を割って話したことを他言しないことだ。口の堅さと友情の強度は比例する。
二)P8:「我々は戦争には負けたが奴隷になったのではない」※当時、敗戦国となった日本にこの気概を持てた日本人が何人いたんだろうか。白洲次郎氏は武士道と騎士道を併せ持ったような人で、今こそこういう気概が必要だと思う。いつまで敗戦国であり続ける必要はない。
三)P15:「弱い奴が強い奴に抑えつけられるのは世の常で致し方なしとしても、言うことだけは堂々と正しいことを言うべきだ」※これは仕事や会社でも同じで、たとえ取引額が大きい客先であっても、理不尽で倫理観に反する要求に対しては、はっきりとお断りするということ。
四)P28:「ようやく戦勝国と対等の立場になれる会議で、その晴れの日の原稿を、相手の承諾を得て相手国の言葉で書く奴がどこにいるんだ!」※これはサンフランシスコ講和条約で首席全権として吉田茂が行う演説の原稿を作った外務省に対する白洲次郎氏の言葉。これは、たとえ負けても日本人としての誇りを持つことの大切さを意味している。
五)P48:「人様に、叱られたり、とやかく言われたくらいで、引っ込む心臓は持ち合わせていない」※SNSやネットが猛威を振るっている昨今、ついつい批判や中傷、軽蔑されることを気にして言いたいことややりたいことを我慢してしまう。白洲次郎氏のような心臓を持ちたい。
六)P58:「困ったときだけ大変だ大変だと大騒ぎして、政府に泣きついてくるが、それで儲かったときは知らぬ顔の半兵衛を決め込む。プリンシプルもなく、走り出したバスに飛び乗るのがうまいだけだ」※これはある種の財界人に対する言葉らしいが、税金を払いたがらないのに助成金や補助金をたかる経営者も同じだ。
七)P60:「人に好かれようと思って仕事をするな。むしろ半分の人間に積極的に嫌われるように努力しないとちゃんとした仕事はできねえぞ」※白洲次郎氏は「リーダーなるべき人間は好かれたら終わり。7割の人間に煙たがられなければ本物ではない」とも言っている。本当にそう思う。経営者は特に。
八)P66:「地位が上がるほど役得ではなく“役損”が増えることを覚えておけ」※こんなことを現代で言うとブラックとかパワハラとか言われそうだが、昔から「ノブレス・オブリージュ」という言葉もある。「位高きは徳高きを要す」という意味だ。
九)P100:「自分より目下と思われる人間には親切にしろよ」※白洲次郎氏は「人が困っているときは助けるもんだ」とも言っている。両方とも当たり前のことだが、実際にいつでもどこでもちゃんと100%出来ているかどうか振り返ると自信がない。肝に銘じておきたい。
十)P152:「本当の友情は腹を割り合った仲にのみ生まれる。相手が好きそうなことばかり言って一時的に相手を喜ばして、してやったりと思っているなど浅はかな極みである」※全くその通り。付け加えると相手が腹を割って話したことを他言しないことだ。口の堅さと友情の強度は比例する。
コメント (0) |トラックバック (0)
トラックバックURL : ボットからトラックバックURLを保護しています
2025年04月09日
一)今読んでいる本がとても面白い。大学院時代の先生がSNSで薦められていた本で『人生後半の戦略書〜ハーバード大学教授が教える人生とキャリアを再構築する方法〜(アーサー・C・ブルックス著/SBクリエイティブ)』という本。
二)私もすでに50歳を過ぎて、情けないことに最近は物忘れも多くなってきた気がしてて、確実に昔より仕事のパフォーマンスも下がってきている。過去の自分の日記を見ると「えっ、そんなにハードスケジュールだったのか」と思うほど、今の私では信じられないくらいの仕事ぶりだったことが分かる。
三)そんなこんなで、いろいろと思うところがあったときに、先生がこの本を薦められていたので早速買って読んでみた。まだ最後まで読み終わっていないが、私が心に留めておきたいと思って線を引いた言葉の一部をこちらに紹介したい。50代を過ぎている方はぜひ原本を読んでもらいたい。※印は私の勝手な所感。
四)P8:『もともとはハードワークの励みになっていたけれど、今では幸福の足かせとなっている要素を手放す』※私はこれがたくさんある苦笑。幸福の足かせとは言わないけれど、起業する頃からストイックに自分へ負荷をかけるようないろんなことを習慣化していた。
五)P40:『自分は「役に立っているとはまったく思わない」もしくは「ほとんど思わない」高齢者は、「役に立っているとよく思う」高齢者に比べ、軽度の障害を発症するリスクが3倍に近く、その研究期間中に亡くなるリスクも3倍以上でした』※世のため人のため何かのために働くことは自分のためになるということ。
六)P44:『仕事依存などの依存症的な行動パターンに陥り、不健全なほどそれにのめり込み、配偶者や子どもや友人との深いつながりを犠牲にしてしまいます(中略)こうして高い目標を達成した人たちは悪循環に陥ります』※私は21歳の時に起業してからずっと仕事依存症だったのでこれまで犠牲にしたものは多いと思う。
七)P78:『私がこれまで見てきた中で、特にたちが悪く毒性の高い依存症は仕事依存症です。(中略)オーツは仕事依存症を「絶え間なく働かなくてはいけないという強迫観念または制御不能な欲求」と定義しました』※少し前まで私も休日に休んでいるとライバルに抜かれそうな気がして何かしら仕事もしくは勉強をしていた。
八)P94:『自分よりも成功している人を見ると負けた気になる、と打ち明ける成功依存症の人がたくさんいます。(中略)社会科学者たちは何十年もの間、地位財では幸福になれないことを明らかにしてきました』※まさしく私のことだ(苦笑)。成功と幸福は全く違う。
九)P172:『50歳のときに最も人間関係に満足していた人々が、80歳のときに最も健康でした』※なるほど。以前読んだ本「グッド・ライフ」にも同じようなことが書かれてあった。人間関係と健康には密接な関係があるということ。これからでもまだまだ間に合う。
十)この本を読んで「成功とは何か」「幸福とは何か」「理想的な人間関係とは」「死んだらどうなるのか」ということを深く考えるいい機会になった。まだ最後まで読み終わっていないので、明日の新幹線の中でゆっくり読みながら、その答えを導き出したい。
二)私もすでに50歳を過ぎて、情けないことに最近は物忘れも多くなってきた気がしてて、確実に昔より仕事のパフォーマンスも下がってきている。過去の自分の日記を見ると「えっ、そんなにハードスケジュールだったのか」と思うほど、今の私では信じられないくらいの仕事ぶりだったことが分かる。
三)そんなこんなで、いろいろと思うところがあったときに、先生がこの本を薦められていたので早速買って読んでみた。まだ最後まで読み終わっていないが、私が心に留めておきたいと思って線を引いた言葉の一部をこちらに紹介したい。50代を過ぎている方はぜひ原本を読んでもらいたい。※印は私の勝手な所感。
四)P8:『もともとはハードワークの励みになっていたけれど、今では幸福の足かせとなっている要素を手放す』※私はこれがたくさんある苦笑。幸福の足かせとは言わないけれど、起業する頃からストイックに自分へ負荷をかけるようないろんなことを習慣化していた。
五)P40:『自分は「役に立っているとはまったく思わない」もしくは「ほとんど思わない」高齢者は、「役に立っているとよく思う」高齢者に比べ、軽度の障害を発症するリスクが3倍に近く、その研究期間中に亡くなるリスクも3倍以上でした』※世のため人のため何かのために働くことは自分のためになるということ。
六)P44:『仕事依存などの依存症的な行動パターンに陥り、不健全なほどそれにのめり込み、配偶者や子どもや友人との深いつながりを犠牲にしてしまいます(中略)こうして高い目標を達成した人たちは悪循環に陥ります』※私は21歳の時に起業してからずっと仕事依存症だったのでこれまで犠牲にしたものは多いと思う。
七)P78:『私がこれまで見てきた中で、特にたちが悪く毒性の高い依存症は仕事依存症です。(中略)オーツは仕事依存症を「絶え間なく働かなくてはいけないという強迫観念または制御不能な欲求」と定義しました』※少し前まで私も休日に休んでいるとライバルに抜かれそうな気がして何かしら仕事もしくは勉強をしていた。
八)P94:『自分よりも成功している人を見ると負けた気になる、と打ち明ける成功依存症の人がたくさんいます。(中略)社会科学者たちは何十年もの間、地位財では幸福になれないことを明らかにしてきました』※まさしく私のことだ(苦笑)。成功と幸福は全く違う。
九)P172:『50歳のときに最も人間関係に満足していた人々が、80歳のときに最も健康でした』※なるほど。以前読んだ本「グッド・ライフ」にも同じようなことが書かれてあった。人間関係と健康には密接な関係があるということ。これからでもまだまだ間に合う。
十)この本を読んで「成功とは何か」「幸福とは何か」「理想的な人間関係とは」「死んだらどうなるのか」ということを深く考えるいい機会になった。まだ最後まで読み終わっていないので、明日の新幹線の中でゆっくり読みながら、その答えを導き出したい。
コメント (0) |トラックバック (0)
トラックバックURL : ボットからトラックバックURLを保護しています
243件中(1件〜5件を表示しています)
前
| 次