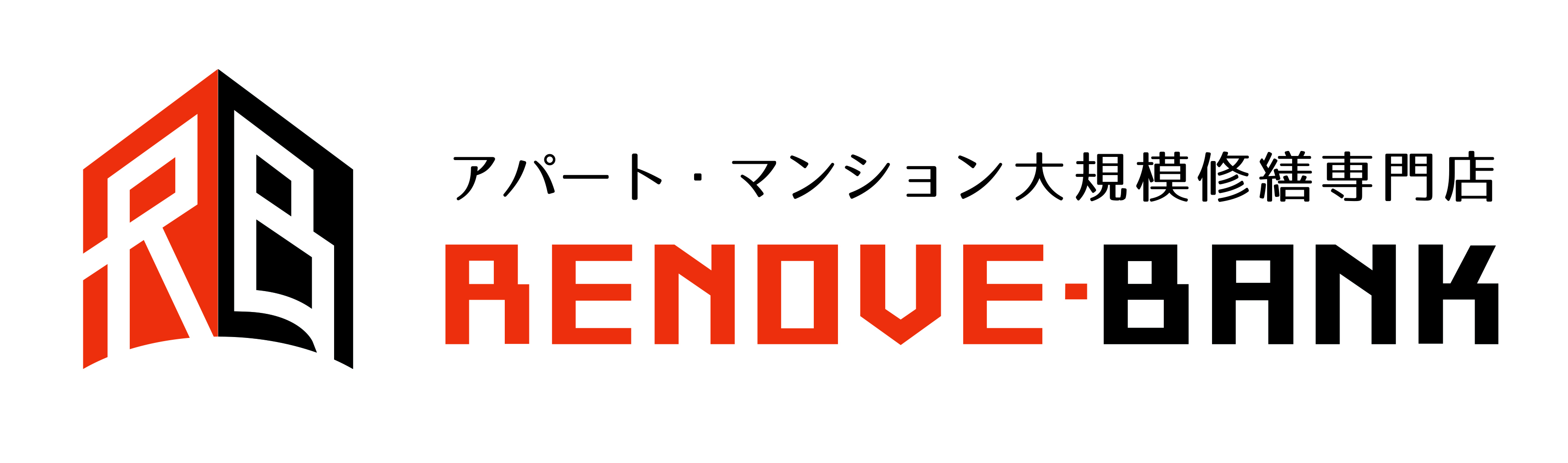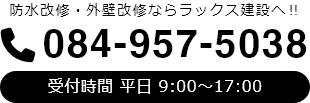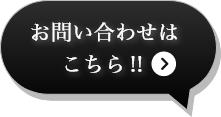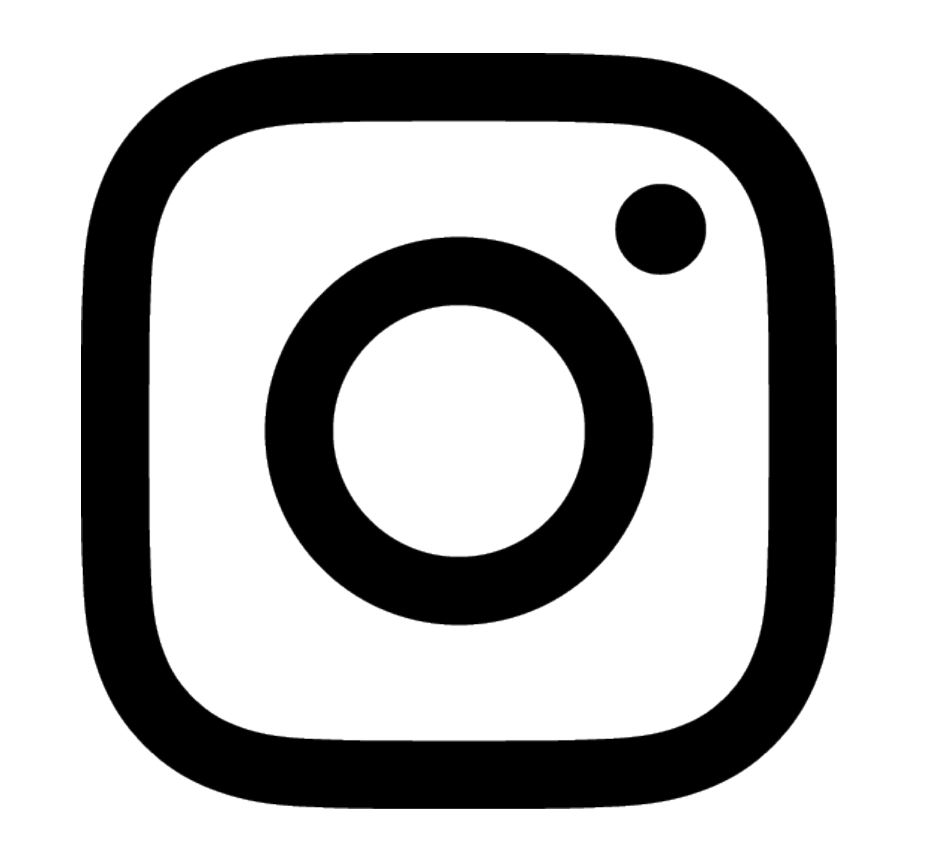一)正直に言うと、昔はマニュアルがあまり好きではなく、人をマニュアルで縛るような気がして、読むのも書くのもめんどくさい。現場は生き物だし、状況に応じて臨機応変に柔軟な対応すればいいと考えていた。いわゆる「良きに計らう」だ。
二)しかし、会社が少しずつ成長してきて、人数も増えて、そうも言ってられなくなった。自分一人や少数でやっていた頃の「阿吽の呼吸」や「なんとなく伝わる感じ」は、まったく通用しなくなり、むしろ、それが原因でミスやトラブルが起きてしまうようになった。
三)それを解消するためにマニュアルや手順書を作成してマネジメントシステムを構築してISO(国際規格)を取得したのが約20年前。それは誰がいつやっても一定の品質が出るようにするための「型」や「ルール」みたいなもので、これがあるかないかで現場の緊張感や仕事の基準が大きく変わった。
四)今はその取得した3つのISOも卒業して国際認証は返上したが、導入しているマネジメントシステムは継続して運用している。現在そのマニュアルや手順書も部門毎にリニューアルに取り掛かっている。これまでの経験や知見、暗黙知などを形式知化して追加するためだ。
五)新人が入ってきたときに、教える人の経験や能力によってバラバラな説明をされると、教わる側も混乱する。しかし、マニュアルがしっかり整備されてあれば、教える方もブレないし、教わる方も理解が深まるし安心できる。現場で判断に迷ったときはマニュアルを見ればいいのだ。
六)もちろん、マニュアルが絶対じゃないし全てじゃない。時によっては現場で想定外のことが起これば、迅速で適切な判断が求められることもあるし「その場で自分で考えて決める力」も育てたい。しかし、それも基準があるからこそ、応用もできるのだと思う。
七)ネガティブに「マニュアルがあるとロボットみたいになる」とか「なんでもかんでもマニュアル通りにすればいい」と言う人もいるが、私は逆だと思ってる。マニュアルがあるからこそ、みんなに裁量や権限を委譲できるのだ。基本の型があるから、安心して動けるし、工夫もできる
八)しかも建設業のような常に現場の環境や状況が変化する仕事は「決めたことを、決めた通りにやる」ことが一番むずかしい。その「決めたこと」を言語化して、誰でも再現できるようにする。それがマニュアルの本当の役割だと思ってる。マニュアルがみんなをリスクから守ってくれるのだ。
九)何かトラブルが起きたときも「ルールどおりにやったか」が確認できる。マニュアルがあるだけで、原因分析も早くなるし、未然防止や再発防止にもつながる。感覚ではなく、仕組みで守る。社員や会社を守るとは、そういうことだと思う。
十)マニュアルは窮屈でみんなを縛るものではなく「次につなぐためのもの」。職人の技術も、営業のノウハウも、管理の工夫も、全部記録して成文化して形式知化しないともったいない。だからマニュアルは立派な知財として常にアップデートしていかなければならないのだ。