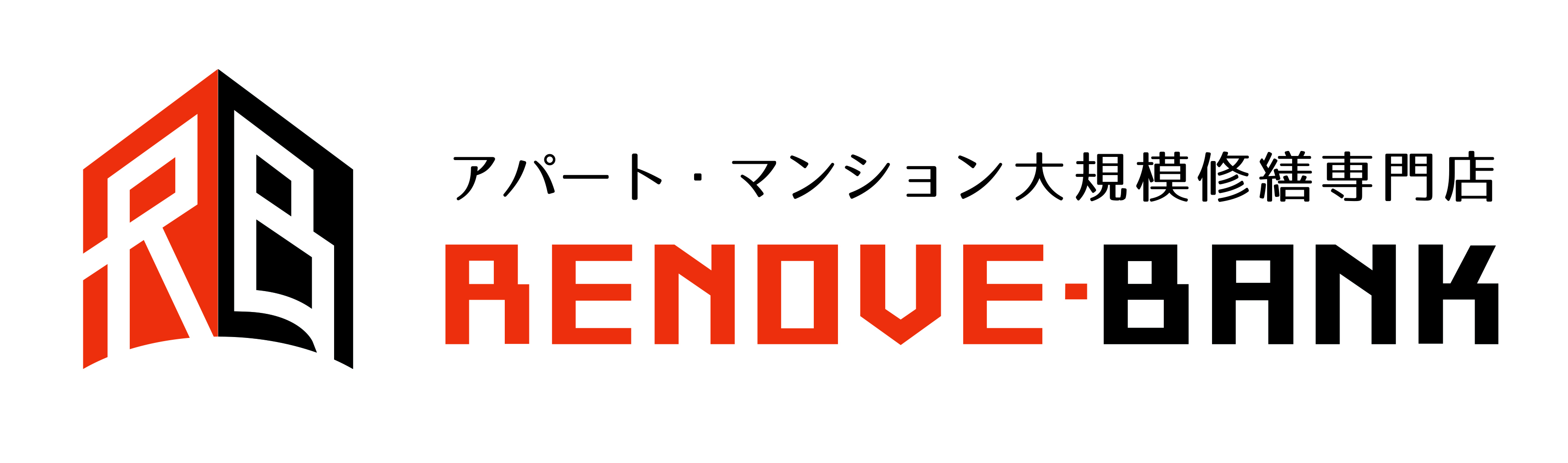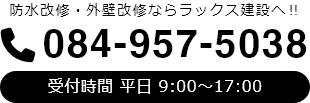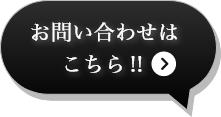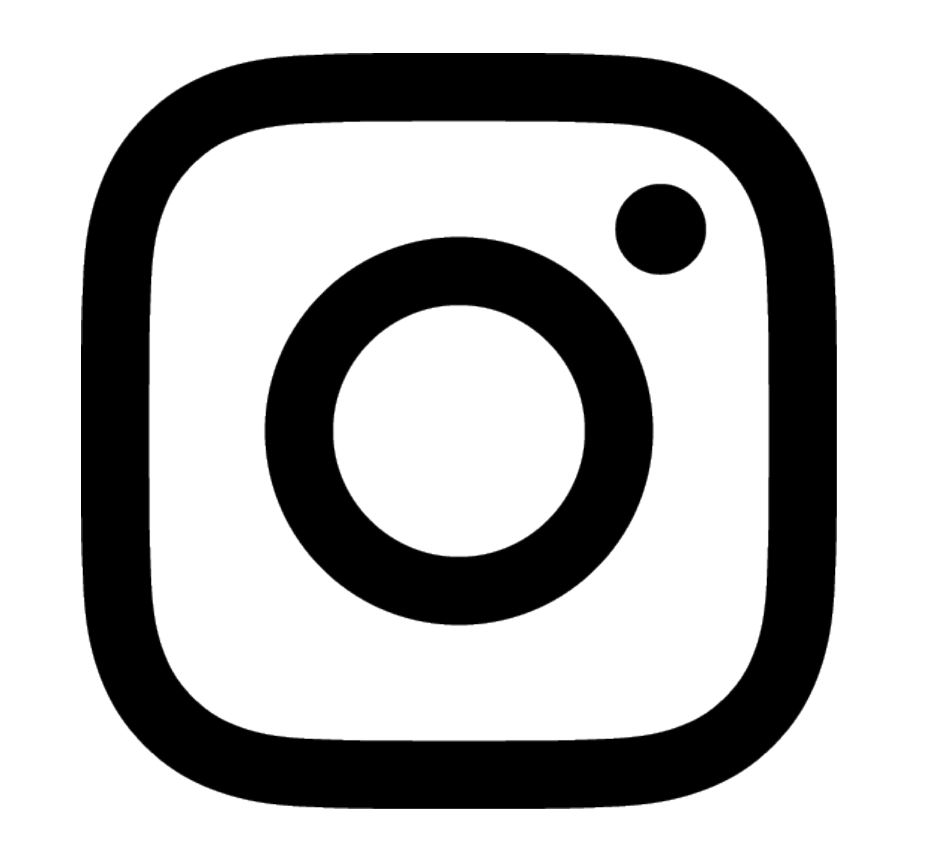2023年03月03日
1)人材育成といえば、ひと昔は「見て覚えろ、見て盗め」で、先輩や師匠から教えてもらうというよりも、一挙手一投足を見逃さないようにしっかり注視して見よう見まねでやってみて、失敗したら叱られて、またやり直してまた叱られるの繰り返し。皆そうやって育てられた。
2)当然、昔はスマホのような便利なものは無かったので、その場ですぐに写真や動画を撮ったり、ググったり、チャットしたり出来なかったので、メモするか覚えるしかなくて、会社や家に帰って現場のことを振り返っては少しずつ覚えていった。
3)だから当時は後輩や部下に「やらせる。任せる」ことが育てることに繋がると信じていた。任せる側(上司や先輩)は多少失敗することを覚悟の上で任せていたし、叱ることも予定通りであり、失敗から学んだり得るものがあると信じていた。
4)けれども最近はそうでもなさそうで「やらせる。任せる」ことが決して育てることではなく「やらさず、任さず」に育てるということが求められているような気がする。それは「育成の効率化」や「精神的成長より論理的思考」が優先されているからだと思う。
5)つまり何でもかんでも効率よく理に適っていないと納得できず動けないから当然、飲み込めない。だから、やらす前に充分な教育と任せる前に念入りな説明が必要になる。初めての料理を食べる前に作り方から食べ方や味、素材、調味料を説明するのと同じだ。
6)私が毎朝読んでいる『生き方の教科書(致知出版社)』という本があって、その中に「理不尽を呑み込む力」という言葉がある。人は理解を超えると理不尽だと感じて動こうとはしないということ。この「理解のレベル」は個人差があり理解を超えないと高まらない。
7)バレーボールにたとえると、練習も100本は理解できても1000本は理解できない。しかし理解できなくても練習を1000本やるチームの方が勝つ。100本の効率的練習よりも、理解を超えた練習を積んだ者だけが圧倒的に成長できるとのこと。
8)私が言いたいことは決して体育会系な働き方を勧めることではなく、自分の「理解のレベル」を超えるためには、先輩や上司からのアドバイスや指示が、たとえ理不尽だと思えても、まず呑み込んでみる動いてみることが大事だということ。はじめから理解できるわけないのだから。
9)たとえ失敗したところで、それは想定内であり評価が下がるわけでもない。学べられる絶好の機会だと捉えるべき。逆にやらない、動かない方が評価が下がると思ったほうがいいし、成長する見込みがない。
10)任されることが「責任を負わされる」と思うのはあまりにも消極的過ぎるし、育てようとしている先輩や上司が可哀想。任せられたら、まず成長する絶好の機会だと捉えて、もし分からなかったら先輩や上司にどんどん食い下がって欲しい。会社をそんなチームにしたい。
2)当然、昔はスマホのような便利なものは無かったので、その場ですぐに写真や動画を撮ったり、ググったり、チャットしたり出来なかったので、メモするか覚えるしかなくて、会社や家に帰って現場のことを振り返っては少しずつ覚えていった。
3)だから当時は後輩や部下に「やらせる。任せる」ことが育てることに繋がると信じていた。任せる側(上司や先輩)は多少失敗することを覚悟の上で任せていたし、叱ることも予定通りであり、失敗から学んだり得るものがあると信じていた。
4)けれども最近はそうでもなさそうで「やらせる。任せる」ことが決して育てることではなく「やらさず、任さず」に育てるということが求められているような気がする。それは「育成の効率化」や「精神的成長より論理的思考」が優先されているからだと思う。
5)つまり何でもかんでも効率よく理に適っていないと納得できず動けないから当然、飲み込めない。だから、やらす前に充分な教育と任せる前に念入りな説明が必要になる。初めての料理を食べる前に作り方から食べ方や味、素材、調味料を説明するのと同じだ。
6)私が毎朝読んでいる『生き方の教科書(致知出版社)』という本があって、その中に「理不尽を呑み込む力」という言葉がある。人は理解を超えると理不尽だと感じて動こうとはしないということ。この「理解のレベル」は個人差があり理解を超えないと高まらない。
7)バレーボールにたとえると、練習も100本は理解できても1000本は理解できない。しかし理解できなくても練習を1000本やるチームの方が勝つ。100本の効率的練習よりも、理解を超えた練習を積んだ者だけが圧倒的に成長できるとのこと。
8)私が言いたいことは決して体育会系な働き方を勧めることではなく、自分の「理解のレベル」を超えるためには、先輩や上司からのアドバイスや指示が、たとえ理不尽だと思えても、まず呑み込んでみる動いてみることが大事だということ。はじめから理解できるわけないのだから。
9)たとえ失敗したところで、それは想定内であり評価が下がるわけでもない。学べられる絶好の機会だと捉えるべき。逆にやらない、動かない方が評価が下がると思ったほうがいいし、成長する見込みがない。
10)任されることが「責任を負わされる」と思うのはあまりにも消極的過ぎるし、育てようとしている先輩や上司が可哀想。任せられたら、まず成長する絶好の機会だと捉えて、もし分からなかったら先輩や上司にどんどん食い下がって欲しい。会社をそんなチームにしたい。
コメント (0) |トラックバック (0)
トラックバックURL : ボットからトラックバックURLを保護しています