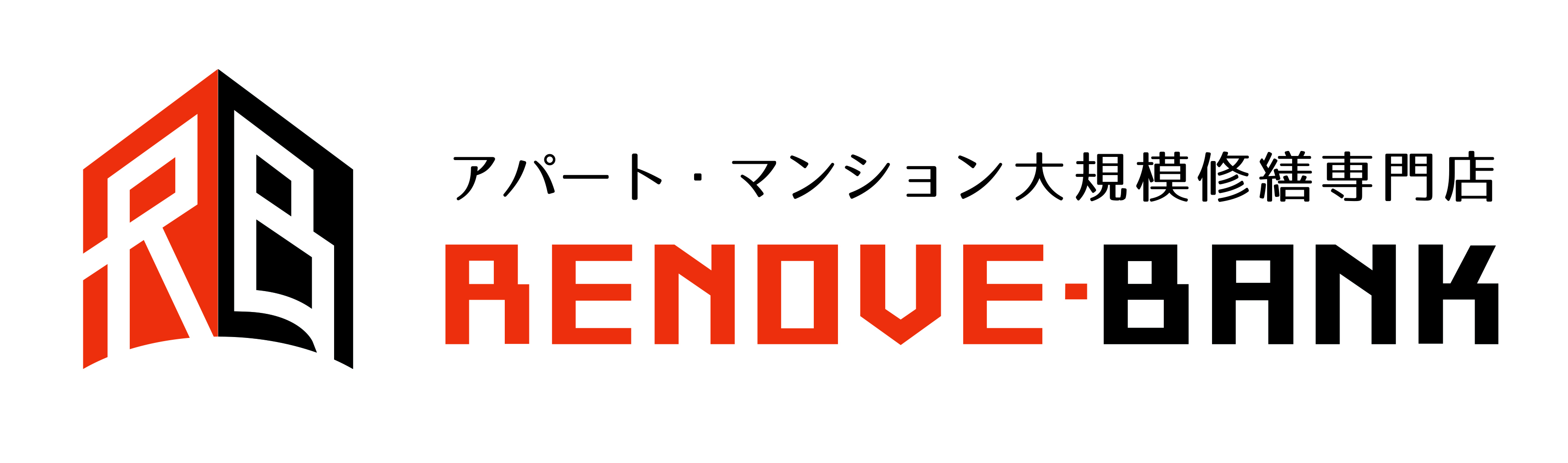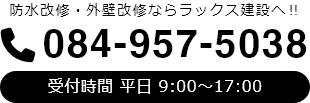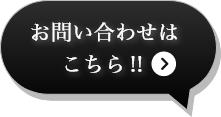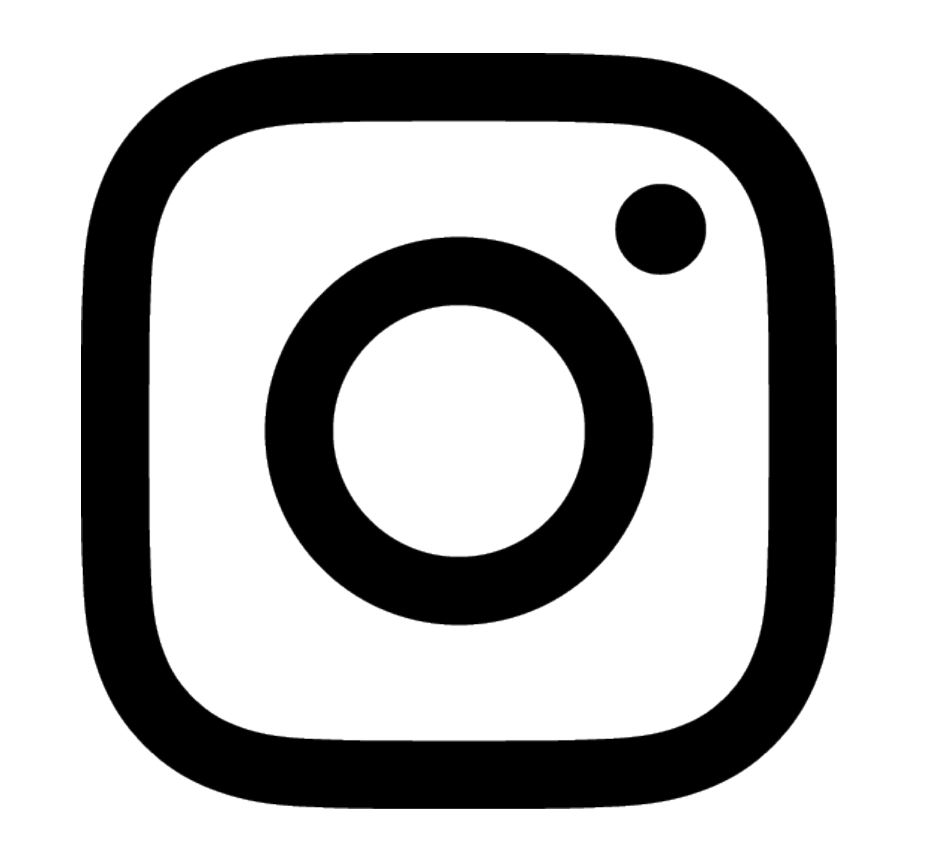ΤσΓΥΗάΛΟΛΩΛΡΛβΛξΓΔ §ΛΪΛΟΛΤΛκΛΡΛβΛξΓΔ≈ΝΛοΛΟΛΤΛκΛ»ΜΉΛΛΙΰΛσΛ«ΛΛΛκΓΘΛ«ΛβΗΫΨλΛœ“ΛΡΛβΛξ”ΛΗΛψΤΑΛΪΛ ΛΛΓΘ≥Έ«ßΛΖΛ ΛΪΛΟΛΩΛ≥Λ»Λ§ΓΔΛΔΛ»Λ«¬γΛ¥Λ»ΛΥΛ ΛκΓΘΛάΛΪΛιΛ≥ΛΫΓΔΛδΛξΛΙΛ°Λ Λ·ΛιΛΛœΟΛΙΛΑΛιΛΛΛ§ΛΝΛγΛΠΛ…ΛΛΛΛΓΘΓ÷ΛΖΛΡΛ≥ΛΛΛ·ΛιΛΛΛ«ΛΝΛγΛΠΛ…ΛΛΛΛΓΉΛ»ΗάΛΠΩΆΛβΛΛΛκΛ§ΓΔΥή≈ωΛΥΛΫΛΈΡΧΛξΛάΛ»ΜΉΛΠΓΘ
ΜΑΓΥΗΫΨλΛ«Αλ»÷¬γΜωΛ ΛΈΛœΓΔΟ ΦηΛξΛ»Ξ≥ΞΏΞεΞΥΞ±ΓΦΞΖΞγΞσΛ«ΛΔΛξΓΔΛΠΛόΛ·œΟΛΜΛ Λ·ΛΤΛβΛΛΛΛΛΪΛιΓΔΛ»ΛΥΛΪΛ·ΧέΛΟΛΤ ζΛ®ΙΰΛόΛ ΛΛΛ≥Λ»ΓΘΚΛΛΟΛΩΛιΫθΛ±ΛρΗΤΛΌΛ–ΛΛΛΛΓΘΕΠΆ≠ΛΙΛκΛ≥Λ»Λ§¬γΜωΓΘΛΠΛόΛ·ΛδΛκ…§ΆΉΛœΛ ΛΛΓΔΛόΛΚάΦΛΥΫ–ΛΜΛ–ΛΛΛΛΓΘ…τ≤ΦΛδΟγ¥÷ΛΪΛιΫθΛ±ΛρΒαΛαΛιΛλΛΩΛιΛΙΛΑΛΥΦξΛρΚΙΛΖΩ≠ΛΌΛκΛ≥Λ»ΛάΓΘ
ΜΆΓΥΞ≥ΞΏΞεΞΥΞ±ΓΦΞΖΞγΞσΛ»ΛœΓΔΨεΦξΛΥΛΖΛψΛΌΛκΛ≥Λ»Λ«ΛœΛ Λ·ΓΔΝξΦξΛρΜΉΛΛΛδΛκΛ≥Λ»ΓΘΛΝΛψΛσΛ» ΙΛ·Λ≥Λ»ΓΘΓ÷ΛΔΛΈΩΆΓΔΛΛΛΡΛβΒΛΛΥΛΪΛ±ΛΤΛ·ΛλΛΤΛκΛ ΓΉΛΟΛΤΜΉΛΟΛΤΛβΛιΛ®ΛκΛΪΛ…ΛΠΛΪΓΘΖκΕ…ΛΈΛ»Λ≥ΛμΓΔΩΆΛΟΛΤ“ ΙΛΛΛΤΛ·ΛλΛΩΩΆ”ΛρΩ°ΆξΛΙΛκΛσΛάΛ»ΜΉΛΠΓΘΛΫΛΠΛδΛΟΛΤΈ…ΙΞΛ ΩΆ¥÷¥ΊΖΗΛρΑιΛΏΓΔΞΝΓΦΞύΞοΓΦΞ·ΛρΕ·Λ·ΛΙΛκΓΘ
ΗόΓΥ¥πΥήΓΔΖζάΏΕ»≥ΠΛΈΩΆ¥÷ΛΟΛΤΗΐ≤ΦΦξΛ§¬ΩΛΛΛΖΓΔΞήΞ≠ΞψΞ÷ΞιΞξΓΦΛ§Ψ·Λ ΛΛΓ Ψ–ΓΥΓΘΛάΛΪΛιΗάΆ’¬≠ΛιΛΚΛ«Λβ…―»ΥΛΥΗάΆ’ΛρΗρΛοΛΙΛ≥Λ»ΓΘΈ©«…Λ Ξ≥ΞΏΞεΞΥΞ±ΓΦΞΖΞγΞσΛ»ΛœΦΝΛηΛξΈΧΛ§¬γΜωΛάΛ»ΜΉΛΠΓΘΩΠΩΆΛ»ΦψΦξΓΔ±ΡΕ»Λ»ΗΫΨλΓΔ≤ώΦ“Λ»ΛΣΒ“ΆΆΓΔΛΫΛ≥ΛΥΛœΛδΛΟΛ―ΛξΓ÷ΗάΆ’ΓΉΛ§…§ΆΉΛΥΛ ΛκΓΘ≈ΝΛ®ΛκΛ≥Λ»ΛρΧΧ≈ίΛ§ΛκΛ»ΓΔΛάΛΛΛΩΛΛΗεΛ«Φξ¥÷Λ§ΝΐΛ®ΛκΓΘ
œΜΓΥΛάΛΪΛιΡΪΈιΛβΛδΛκΛΖΓΔΞΏΓΦΞΤΞΘΞσΞΑΛβΛδΛκΛΖΓΔΗΠΫΛ≤ώΛβΛδΛκΛΖΓΔΜΰΛΥΛœΩ©Μω≤ώΛβΛδΛκΓΘΜ®ΟΧΛΈΟφΛΥΥή≤ΜΛ§ΛΔΛκΛ≥Λ»Λβ¬ΩΛΛΓΘΛΩΛΟΛΩΑλΗάΛΈΓ÷ΛΔΛξΛ§Λ»ΛΠΓΉΓ÷¬γΨφ…ΉΓ©ΓΉΛ«ΓΔΕθΒΛΛ§Ξ§ΞιΞΟΛ» ―ΛοΛκΛ≥Λ»ΛβΛΔΛκΓΘΨ°ΛΒΛ Ψ·Λ ΛΛΗάΆ’Λ«Λβ¥ΊΖΗά≠Λ§Έ…Λ·Λ ΛκΓΘΛΫΛλΛ§ΩΠΨλΛ«ΛœΛ»ΛΤΛβ¬γάΎΛ Λ≥Λ»ΓΘ
ΦΖΓΥΞόΞΥΞεΞΔΞκΛβ¬γΜωΓΔΜ≈Ν»ΛΏΛβ¬γΜωΓΘΛ«ΛβΛΫΛλΛάΛ±ΛΗΛψΨεΦξΛ·ΤΑΛΪΛ ΛΛΛΈΛ§“ΩΆ¥÷ΛΈΫΗΛόΛξ”Λ»ΛΛΛΠΛβΛΈΓΘΦξΛρΤΑΛΪΛΙΛΈΛœΩΆΓΘΜ≈ΨεΛ≤ΛκΛΈΛβΩΆΓΘΛάΛΪΛιΓ÷ΩΆΛ»ΩΆΓΉΛΈΜθΦ÷Λ§ΛΠΛόΛ·≤σΛΟΛΤΛ ΛΛΛ»ΓΔΛ…Λ≥ΛΪΛ«œΡΛΏΛ§Ϋ–ΛκΓΘΞ≥ΞΏΞεΞΥΞ±ΓΦΞΖΞγΞσΛœΛΫΛΈΫα≥ξΧΐΛΏΛΩΛΛΛ ΛβΛΈΛάΓΘ
»§ΓΥάΈΛηΛξΞαΓΦΞκΛβΞΝΞψΞΟΞ»ΛβΝΐΛ®ΛΤΓΔΛ»ΛΤΛβ ΊΆχΛΥΛœΛ ΛΟΛΩΛ±Λ…ΓΔΛδΛΟΛ―Λξ“¥ιΛρΗΪΛΤœΟΛΙ”ΛΟΛΤΛΛΛΠΛΈΛœΓΔΛ Λ·ΛΖΛΤΛœΛΛΛ±Λ ΛΛΛ Λ»ΜΉΛΠΓΘΤΟΛΥΞ»ΞιΞ÷ΞκΛ§Β·Λ≠ΛΩΛ»Λ≠ΛέΛ…ΓΔΞαΓΦΞκΛδ≈≈œΟΛΗΛψΛ Λ·ΓΔΛΝΛψΛσΛ»≤ώΛΟΛΤœΟΛΖΛΩ ΐΛ§ΛΛΛΛΓΘ ΊΆχΛΒΛΈ±ΔΛ«ΓΔ≈ΝΛ®ΛκΛΌΛ≠Λ≥Λ»Λ§Λ≥ΛήΛλΆνΛΝΛΤΛΛΛ ΛΛΛΪΓΔΒΛΛρΛΡΛ±Λ ΛΛΛ»ΛΛΛ±Λ ΛΛΓΘ
ΕεΓΥΖκΕ…ΓΔ≤ώΦ“ΛœΩΆΛΈΫΗΙγ¬ΈΛάΛΪΛιΓΔΗΫΨλΛβΓΔ≤ώΒΡΛβΓΔΟ ΦηΛξΛβΓΔΛΙΛΌΛΤΓ÷ΩΆΛ»ΩΆΓΉΛ§≥ζΛΏΙγΛΟΛΤΫιΛαΛΤ≤σΛκΓΘΛΫΛΈ≥ζΛΏΙγΛοΛΜΛρΈ…Λ·ΛΙΛκΛΈΛ§ΓΔΤϋΓΙΛΈ≤ώœΟΛδΜ®ΟΧΛάΛΟΛΩΛξΛΙΛκΓΘ≤ΩΛρœΟΛΖΛΩΛΪΛηΛξΛβΓΔΟ·Λ»œΟΛΜΛκΛΪΓΘΛΫΛΈ¥ΊΖΗά≠Λ§ΓΔΛΛΛΛΗΫΨλΓΔΛΛΛΛΩΠΨλΛρΛΡΛ·ΛκΛΈΛάΛ»ΜΉΛΠΓΘ
ΫΫΓΥάΦΛρΛΪΛ±ΛκΓΘ ΙΛ·ΦΣΛρΛβΛΡΓΘ≥Έ«ßΛρ¬’ΛιΛ ΛΛΓΘΛΫΛλΛάΛ±Λ«ΓΔΜ≈ΜωΛœΕΟΛ·ΛέΛ…ΞΙΞύΓΦΞΚΛΥΛ ΛκΓΘœΟΛΒΛ ΛΛΛ»≈ΝΛοΛιΛ ΛΛΛΖΓΔ≈ΝΛ®Λ ΛΛΛ»ΜœΛόΛιΛ ΛΛΓΘΛάΛΪΛιΓΔΨοΛΥΛΝΛψΛσΛ»œΟΛΙΛ≥Λ»ΛΪΛιΜœΛαΛΤΛέΛΖΛΛΛ»ΜΉΛΠΓΘΛόΛΚΛœΑλΗάΓΔΓ÷Ρ¥Μ“Λ…ΛΠéùΛΪΛιΛ«ΛβΛΛΛΛΓΘΛΫΛλΛάΛ±Λ«ΓΔΕθΒΛΛ§ΤΑΛ≠Ϋ–ΛΙΛΈΛάΓΘ
ΤσΓΥΛ≥ΛΈΤ±Φ“ΕδΚ¬≈ΙΛΈ≈Ι όΙ©ΜωΑλΦΑΛρΑ ΝΑ άΦ“Λ«ΜήΙ©ΛΒΛΜΛΤΡΚΛΛΛΩΓΘΛ≥ΛΈ¬ΨΛΥΛβΤ±Φ“≤Θ…Ά≈ΙΛΈΤβΝθ δΫΛΙ©ΜωΛδΥήΦ“Ι©ΨλΛΈ¬γΒ§ΧœΞλΞΛΞΔΞΠΞ» ―ΙΙΙ©ΜωΛ Λ…ΛβΛΣΦξ≈ΝΛΛΛΒΛΜΛΤΡΚΛΛΛΤΛΣΛξΓΔΛΛΛΡΛβΛΣάΛœΟΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘΛάΛΪΛιΤ±Φ“ΛΈΩ ≤ΫΛ÷ΛξΛΥΛœΛΛΛΡΛβΕΟΛΪΛΒΛλΛΤΛΛΛκΓΘ
ΜΑΓΥΛΫΛΈΤ±Φ“ΛΈΤΘΑφΦ“ΡΙΛΥΛœΧ«¬ΩΛΥΛΣ≤ώΛΛΛ«Λ≠ΛκΒΓ≤ώΛœΛ ΛΛΛ§ΓΔΛ≥ΛΈ≈ΌΫ–»«ΛΒΛλΛΩΟχΫώΛρ«“Τ…ΛΖΛΤΓΔΤ±Φ“Λ§ά°ΡΙΛΖ¬≥Λ±ΛκΆΐΆ≥Λ§ΛηΛ· §ΛΪΛΟΛΩΒΛΛ§ΛΙΛκΓΘΜδΛ§Τ±ΫώΛρΤ…ΛσΛ«ΞΈΓΦΞ»ΛΥΞαΞβΛΖΛΩΗάΆ’ΛΈΑλ…τΛρΛ≥Λ≥Λ«Λ¥Ψ“≤πΛΖΛΩΛΛΓΘΛΦΛ“Λ¥ΑλΤ…Λρ¥ΪΛαΛκΓΘΓ Δ®ΑθΛœΜδΛΈΨΓΦξΛ Ϋξ¥ΕΛ ΛΈΛ«ΤΘΑφΦ“ΡΙΛΈΛ¥Α’ΗΰΛ»ΛœΝ¥Λ·¥ΊΖΗΛ ΛΛΓΥ
ΜΆΓΥP6ΓßΜδΛΩΛΝΛœΨΠ… ≈Η≥ΪΛΈΞΤΓΦΞόΛΥΓ÷No Place Like HomeΓΉΛ»ΛΛΛΠΗάΆ’ΛρΖ«Λ≤ΛΤΛΛΛόΛΙΓΘ(ΟφΈ§)œ¬ΧθΛΙΛλΛ–Γ÷≤»ΛΥΛΪΛ ΛΠΛβΛΈΛ ΛΖΓΉΓΘΛβΛΟΛ»Λ·ΛάΛ±ΛΩΗάΛΛ ΐΛρΛΙΛλΛ–Γ÷ΛοΛ§≤»Λ§ΛΛΛΝΛ–ΛσΓΉΛ»ΛΛΛΟΛΩ¥ΕΛΗΛ«ΛΖΛγΛΠΛΪΓΘΓ Δ® άΦ“ΛΈΖ–±ΡΆΐ«ΑΓ÷Φ“ΑςΛ»≤»¬≤Λρ¬ηΑλΛΥΙΆΛ®ΛηΛΠ(Φ“ΑςΙ§ Γ)ΓΉΛ»ΕΠΡΧΛΙΛκΗάΆ’ΛάΛ»ΜΉΛΠ)
ΗόΓΥP16ΓßΘΝΘΥΘΝΘ”Θ≈ Θ«Θ“ΘœΘ’Θ–ΛœΨΠ… Λ§«δΛλΛΤΛΣ≈ΙΛ§ΝΐΛ®ΛκΛάΛ±Λ«ΛœΓΔΖηΛΖΛΤΥΰ¬≠ΛΖΛόΛΜΛσΓΘΜδΛΩΛΝΛœάΫ… ΛδΞΒΓΦΞ”ΞΙΛρΡΧΛΗΛΤΓΔΙ§ΛΜΛ κΛιΛΖΛρΝœ¬ΛΛΙΛκΛΈΛ«ΛΙΓΘ(Δ®Λ≥ΛΈΗάΆ’Λβ άΦ“ΛΈΞΏΞΟΞΖΞγΞσΛ«ΛΔΛκΓΊΑ¬Ν¥Λ Ζζ ΣΓΔΑ¬Ω¥Λ άΗ≥ηΓΔΑ¬ΡξΛΖΛΩ¥ΡΕ≠ΛρΝœ¬ΛΛΙΛκΓΌΛ»Τ±ΒΝΗλΛάΛ»ΜΉΛΠΓΥ
œΜΓΥP66ΓßΛΡΛόΛξΓΔΛ’ΛΩΛξΛ§Γ÷ΦΪ §ΛΩΛΝΛ§ΆΏΛΖΛΛΛβΛΈΓΉΛ»ΛΖΛΤΚνΛΟΛΩΞΤΓΦΞ÷ΞκΛœΓΔΖκ≤Χ≈ΣΛΥΓΔΟ·ΛβΗΪΛΩΛ≥Λ»Λ§Λ ΛΛΛηΛΠΛ ΨΠ… ΛάΛΟΛΩΛΈΛ«ΛΙΓΘΓ Δ®Γ÷Λ’ΛΩΛξΓΉΛ»ΛœΜδΛ§ΛΣάΛœΟΛΥΛ ΛΟΛΩΗεΤΘ…ϊΦ“ΡΙΛ»Μ≥ΥήΗΒΨοΧ≥ΛΈΛ≥Λ»ΓΘΛ≥ΛΈΛΣΤσΩΆΛ§≤ώΦ“ΛΥΑλά–Λρ≈ξΛΗΛΤΚνΛΟΛΩΨΠ… Λ§¬γΞ“ΞΟΞ»ΛΖΛΤΩΖΛΖΛΛΞ÷ΞιΞσΞ…Λ§Ϋ–ΆηΛΩΛ»ΛΈΛ≥Λ»ΓΘΛΠΛΝΛβΛ≥ΛΈΛΣΤσΩΆΛΈΛηΛΠΛ Φ“ΑςΛρΒαΛύ)
ΦΖΓΥP86ΓßΞ÷ΞιΞσΞ…Λρ¬«ΛΝΈ©ΛΤΛκΛΩΛαΛΥΛβΓΔΓ÷Λ≥ΛλΑ ΨεΛΈΝ«ΚύΛœΛ ΛΛΓΉΛ»ΗάΛ®ΛκΞλΞΌΞκΛΥΛΖΛηΛΠΛ»ΖηΑ’ΛΖΛόΛΖΛΩΓΘ(Δ®Ε»≥ΠΛ§Ν¥Λ·ΑψΛΠΛ§ΛΠΛΝΛΈ≤ώΦ“ΛΥΟ÷Λ≠¥ΙΛ®ΛκΛ»Γ÷Λ≥ΛλΑ ΨεΛΈ… ΦΝΛ»ΞΒΓΦΞ”ΞΙΛœΛ ΛΛΓΉΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΓΘΛΠΛΝΛβΓ÷ΞξΞΈΞΌΞ–ΞσΞ·Γ÷Λ»Γ÷Θ“Θ≈ΘΈΘœΘ÷Θ≈ΘΧΘΧ(ΞξΞΈΞΌΓΦΞκ)ΓΉΛ»ΛΛΛΠΤσΛΡΛΈΞΣΓΦΞ ΓΦ ΧΞ÷ΞιΞσΞ…ΛρΈ©ΛΝΨεΛ≤ΛΤΛΛΛκ)
»§ΓΥP181ΓßΩΆΛ§ΑιΛΤΛ–≤ώΦ“Λ§ΑιΛΡΛΖΓΔ≤ώΦ“Λ§ΑιΛΤΛ–ΩΆΛβΑιΛΡΓΘΛ≥ΛΈΞΒΞΛΞ·ΞκΛρ≤σΛΙΛΈΛ§Ζ–±ΡΦ‘ΛΈΜ≈ΜωΛ«ΛΙΓΘ(Δ®Λ≥ΛΈΗάΆ’ΛœΖ–±ΡΦ‘ΛΈΟΦΛ·ΛλΛΈΜδΛΥΛβΜ…ΛΒΛΟΛΩΓΘΝ¥Λ·ΛΫΛΈΡΧΛξΛ«ΓΔΩΆΛœΛΏΛσΛ ά°ΡΙΛΖΛΩΛΛΛ»ΜΉΛΟΛΤΛΛΛκΛΖΓΔά°ΡΙΛ«Λ≠Λκ≤ώΦ“ΛρΒαΛαΛκΓΘά°ΡΙΛΖΛΩΛΛΩΆΛ§Τ·Λ·ΛΪΛι≤ώΦ“Λβά°ΡΙΛΙΛκΛΈΛάΓΘΛ≥ΛΈΜ≈Ν»ΛΏΛρΚνΛκΛΈΛ§ΜδΛΈΜ≈ΜωΛ ΛΈΛάΓΥ
ΕεΓΥP185ΓßΞόΞΙΞΩΓΦΞΠΞ©ΓΦΞκΛ§Ι§ΛΜΛ ≤»ΡμΛ»Λ»ΛβΛΥ βΛύΞ÷ΞιΞσΞ…Λ«ΛΔΛκΛ ΛιΓΔ≤ώΦ“ΛβΛόΛΩΙ§ΛΜΛ ≤»ΡμΛ≈Λ·ΛξΛΥΙΉΗΞΛ«Λ≠Λκ¬ΗΚΏΛ«Λ±ΛλΛ–Λ ΛιΛ ΛΛΛΈΛ«ΛΙΓΘΓ Δ®ΛΠΛΝΛ§ΜΆΛΡΛΈΖ–±ΡΆΐ«ΑΛΈΛΠΛΝΓ÷Φ“ΑςΛ»≤»¬≤Λρ¬ηΑλΛΥΙΆΛ®ΛηΛΠ(Φ“ΑςΙ§ Γ)ΓΉΛρΑλ»÷ΛΥΖ«Λ≤ΛκΆΐΆ≥ΛœΓΔΛόΛΒΛΖΛ·Λ≥ΛΈΤΘΑφΦ“ΡΙΛΈΗάΆ’ΛΈΡΧΛξΛάΓΥ
ΫΫΓΥΛ≥ΛΈ≈ΌΓΔΤ±ΫώΛρ«“Τ…ΛΖΛΤΓΔ≤ΰΛαΛΤΜ≈ΜωΛ»ΛœΓΔ≤»ΡμΛ»ΛœΓΔ≤ώΦ“Λ»ΛœΓΔΦ“ΑςΛ»ΛœΓΔΖ–±ΡΦ‘Λ»ΛœΛ…ΛΠΛΔΛκΛΌΛ≠ΛΪΓΔΚΘΛόΛ«ΛρΩΕΛξ ÷ΛκΛΛΛΛΒΓ≤ώΛΥΛ ΛΟΛΩΛΖΓΔΛφΛΟΛ·ΛξΙΆΛ®ΛκΛ≥Λ»Λ§Ϋ–ΆηΛΩΓΘΩΆΛœΩΆάΗΛΈΞ÷ΞιΞσΞ«ΞΘΞσΞΑΛρΓΔ≤ώΦ“ΛœΜ≈ΜωΛΈΞ÷ΞιΞσΞ«ΞΘΞσΞΑΛρΛΖΛΤΛΛΛΪΛ Λ±ΛλΛ–Λ ΛιΛ ΛΛΓΘ
ΤσΓΥP5ΓßΛ≥Λ≥Λ«≈ΝΛ®ΛΤΛΣΛ≠ΛΩΛΛΛΈΛ§Γ÷≤ΝΟΆΛœ3ΛΡΛΔΛκΓΉΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»Λ«ΛΙΓΘΛΫΛλΛœ¥ϊ¬Η≤ΝΟΆΓΔ…’≤Ο≤ΝΟΆΓΔ…‘ΆΉ≤ΝΟΆΛ«ΛΙΓΘΓ÷¥ϊ¬Η≤ΝΟΆΓαΝέΡξΤβΛΈ≤ΝΟΆΓΉΓ÷…’≤Ο≤ΝΟΆΓαΝέΡξ≥ΑΛΈ≤ΝΟΆΓΉΓ÷…‘ΆΉ≤ΝΟΆΓα…’≤Ο≤ΝΟΆΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛ ΛΛΛ≥Λ»ΓΉΓΓΔ®Λ≥ΛΈ…’≤Ο≤ΝΟΆΛρΝœ¬ΛΛΙΛκΛ≥Λ»Λ§ΜδΛΩΛΝΛΈΜ≈ΜωΛ«ΛΔΛξΓΔΞΝΓΦΞύΞοΓΦΞ·ΛΈΑ“ΈœΛρ»·¥χΛΙΛκΛ»Λ≥ΛμΓΘ
ΜΑΓΥP36Γß…’≤Ο≤ΝΟΆΛρΛΡΛ·ΛλΛ–ΓΔΞ≥ΞβΞ«ΞΘΞΤΞΘ≤Ϋ(Αλ»Χ≤Ϋ)ΛΒΛλΛΤΛΖΛόΛΟΛΩΛβΛΈΛΈΧΞΈœΛρΩΖΛΩΛΥΛΡΛ·ΛξΡΨΛΙΛ≥Λ»ΛβΛ«Λ≠ΓΔΞλΞΟΞ…ΞΣΓΦΞΖΞψΞσΛ«ΛΈάοΛΛΛρΞ÷ΞκΓΦΞΣΓΦΞΖΞψΞσΛΥΑήΛΙΛ≥Λ»ΛβΛ«Λ≠ΛκΛΪΛβΛΖΛλΛόΛΜΛσΓΘΔ®Ξ÷ΞκΓΦΞΣΓΦΞΖΞψΞσΛΥΑήΛλΛ–ΕΞΙγΛ§ΛΛΛ ΛΛΛΈΛ«≤Ν≥ ΕΞΝηΛβΛΙΛκΛ≥Λ»Λ Λ·ΓΔΛΏΛσΛ Λ«≥ΎΛΖΛ·ΛΈΛ”ΛΈΛ”Λ»Μ≈ΜωΛ§Λ«Λ≠ΛκΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»(Ψ–)ΓΘ
ΜΆΓΥP78ΓßΛ ΛΛΛβΛΈΛΥΜκ≈άΛρΛρΗΰΛ±ΛκΛΈΛ«ΛœΛ Λ·ΓΔΛΔΛκΛβΛΈΛρ…’≤Ο≤ΝΟΆ≤ΫΛΖΛΤΛΛΛ·ΓΘΔ®Λ ΛΛΛβΛΈΛ–ΛΪΛξΛΥΧήΛρΗΰΛ±ΛΤΧΒΆΐΛρΛΖΛΤΦξΛΥΤΰΛλΛΩΛ»Λ≥ΛμΛ«¥ Ο±ΛΥΛœΡξΟεΛΖΛ ΛΛΓΘΈΌΛΈΦ«Λ§άΡΛ·ΗΪΛ®ΛκΛΈΛ»Τ±ΛΗΓΘΚΘΛΔΛκΛβΛΈΛρΗΠΛ°άΓΛόΛΜΓΔΥαΛ≠ΛόΛ·ΛκΛ≥Λ»Λ«ΆΘΑλΧΒΤσΛΈΛβΛΈΛ§άΗΛόΛλΛκΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΓΘΛΫΛλΛρ≤Ρ«ΫΛΥΛΙΛκΛΈΛ§Χ¥ΛδΜ÷ΛΈΈœΛάΛ»ΜΉΛΠΓΘ
ΗόΓΥP79ΓßΦ≠ΫώΛ«Γ÷Μ≈ΜωΓΉΛρΡ¥ΛΌΛΤΛΏΛκΛ»Λ≥ΛΠΚήΛΟΛΤΛΛΛόΛΖΛΩΓΘ≠Γ≤ΩΛΪΛρΚνΛξΫ–ΛΙΓΔΛόΛΩΛœά°ΛΖΩκΛ≤ΛκΛΩΛαΛΈΙ‘ΤΑΓΘ≠ΔάΗΖΉΛρΈ©ΛΤΛκΦξΟ Λ»ΛΖΛΤΫΨΜωΛΙΛκΜω ΝΓΘΩΠΕ»ΓΘ≠ΘΛΖΛΩΛ≥Λ»ΓΘΙ‘ΤΑΛΈΖκ≤ΧΓΘΕ»ά”ΓΘΔ®Λ≥ΛΈ3ΛΡΛΈΛΠΛΝΓΔ…’≤Ο≤ΝΟΆΛ»ΛœΛόΛΒΛΖΛ·Λ≥ΛΈ≠ΓΛάΛ»ΜΉΛΠΓΘΛΛΛΡΛΈΜΰ¬εΛβΛ…ΛΈΕ»≥ΠΛβΜ≈ΜωΛ»Λœ…’≤Ο≤ΝΟΆΛρΚνΛξΫ–ΛΙΛ≥Λ»ΓΘΛβΛΝΛμΛσΜδΛΩΛΝΛβΤ±ΛΗΓΘ
œΜΓΥP83ΓßΦΐΤΰΛρΨεΛ≤ΛΩΛ±ΛλΛ–ΓΔΡσΕΓΛ«Λ≠Λκ…’≤Ο≤ΝΟΆΛρΙβΛαΛκΛ≥Λ»ΓΘΜ≈ΜωΛ«ά°≤ΧΛρΫ–ΛΖΛΩΛΛΨλΙγΛβΡσΕΓΛ«Λ≠Λκ…’≤Ο≤ΝΟΆΛρΙβΛαΛκΛ≥Λ»Λ«ΛΙΓΘΔ®«δΨεΛδΟΆΟ ΓΔ σΫΖΛβΛΙΛΌΛΤ…’≤Ο≤ΝΟΆΛ«ΖηΛόΛκΛ»ΗάΛΟΛΤΛβ≤αΗάΛ«ΛœΛ ΛΛΓΘΤ±ΛΗΨΠ… ΓΔΤ±ΛΗΞΒΓΦΞ”ΞΙΛ«Λβ«δΛκΩΆΓΔ«δΛξ ΐΓΔ«δΛκΫξΛ§ ―ΛοΛλΛ–ΧΌΛ±Λβ ―ΛοΛκΓΘΛ≥ΛλΛ§…’≤Ο≤ΝΟΆΓΘ
ΦΖΓΥP152ΓßΦΪ §Λ«ΦΪ §ΛΈΕ·ΛΏΛ§ §ΛΪΛξΛΥΛ·ΛΛΙΫ¬ΛΛ§ΛΔΛξΛόΛΙΓΘΛΫΛλΛœΓΔ¬ΨΦ‘Λ»»φ≥”ΛΖΛΤΕ·ΛΏΛΥΛ ΛΟΛΤΛΛΛκΛηΛΠΛ Λ≥Λ»Λ«ΛβΓΔΦΪ §ΛΥΛ»ΛΟΛΤΛœ…αΡΧΛΈΛ≥Λ»ΛΙΛ°ΛΤΓΔΕ·ΛΏΛάΛ»ΒΛΛ≈ΛΪΛ ΛΛΨλΙγΛ§ΛΔΛκΛΈΛ«ΛΙΓΘΔ®ΛάΛΪΛιΗήΒ“ΞΔΞσΞ±ΓΦΞ»ΛœΫ≈ΆΉΛάΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΓΘΗήΒ“Λœ≤ΩΗΈΛΠΛΝΛΥΟμ ΗΛΖΛΤΛ·ΛλΛΩΛΈΛΪΓΔ≤ΩΗΈΛΠΛΝΛΗΛψΛ ΛΛΛ»ΛΛΛ±Λ ΛΪΛΟΛΩΛΈΛΪ(Ε·ΛΏ)Λ§ §ΛΪΛκΓΘ
»§ΓΥΘ–194ΓßΛΣΒ“ΛΒΛσΛΥΩ‘Λ·ΛΙΛ≥Λ»ΛΪΛιΜœΛαΛκΓΘΛΫΛΈΛΩΛαΛΥΛœΓΔΛΣΒ“ΛΒΛσΛΈ¥νΛ”ΛΈΝ«ΛρΙΆΛ®ΛΤΛΛΛ·ΓΘΛ≥ΛλΛβ…’≤Ο≤ΝΟΆ≤ΫΛ«¬γάΎΛ Λ≥Λ»Λ«ΛΙΓΘΔ®Λ…ΛσΛ ΨΠ«δΛβΓ÷ΛΣΒ“ΛΒΛσΓΉΛΪΛι«ψΛΟΛΤΛβΛιΛοΛ ΛΛΛ»Μΐ¬≥Λ«Λ≠Λ ΛΛΛΖά°ΛξΈ©ΛΩΛ ΛΛΓΘ«ψΛΟΛΤΛβΛιΛΠΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»Λœ¥νΛσΛ«ΛβΛιΛΠΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΓΘ≈ωΛΩΛξΝΑΛάΛ±Λ…¥νΛσΛ«ΛβΛιΛ®Λ ΛΛΛ»ΦΓΛΪΛι«ψΛΟΛΤΛβΛιΛ®Λ ΛΛΓΘ
ΕεΓΥP228ΓßΦΪ §ΛΩΛΝΛΥΛ»ΛΟΛΤΛΈΓ÷≈ωΛΩΛξΝΑΓΉΛ§≥ΑΛΪΛιΗΪΛΩΛιΓ÷…’≤Ο≤ΝΟΆΓΉΛΥΛ ΛξΓΔΛόΛΩΓ÷ΟΜΫξΛœΓΔΡΙΫξΛΥΛβΛ ΛκΓΉΛ»ΛΛΛΠΙΆΛ® ΐΛ«ΛΙΓΘΔ®Ψ°ΛΒΛΛΝ»ΩΞΛ«ΛβΨ°≤σΛξΛ§ΆχΛΛΛΤ¬–±ΰΛ§Αλ»÷Έ…ΛΪΛΟΛΩΛξΛΙΛκΛΖΓΔΞαΞΥΞεΓΦΛ§Ψ·Λ ΛΛΑϊΩ©≈ΙΛ«ΛβΟœΑηΛ«Αλ»÷ΛΈΑλ… Λ§Ϋ–ΛΜΛκ≈ΙΛβΛΔΛκΓΘ…’≤Ο≤ΝΟΆ≤ΫΛ»ΛœΖηΛΖΛΤΤώΛΖΛΛΛ≥Λ»Λ«ΛœΛ ΛΛΓΘΡσΕΓΛΙΛκ¬ΠΛΈΑ’Φ±ΛΈΧδ¬ξΛάΓΘ
ΫΫΓΥΔ®ΛΠΛΝΛΈΨ≠ΆηΛœΛ≥ΛΈ…’≤Ο≤ΝΟΆΛρΛ…ΛλΛάΛ±άΗΛΏΫ–ΛΜΛκΛΪΛΥΛΪΛΪΛΟΛΤΛΛΛκΓΘΛΫΛΈΛΩΛαΛΥΛœΦψΛΛΩΆΛδΩΖΩΆΛΈΩΖΛΖΛΛΜκ≈άΛδ¥ΕΛΗ ΐΓΔ¥Εά≠ΛβΫ≈ΜκΛΖΛ ΛΛΛ»ΛΛΛ±Λ ΛΛΛ»ΜΉΛΠΓΘΖηΛΖΛΤΞΌΞΤΞιΞσΛδΫœΈΐΦ‘ΛάΛ±Λ§…’≤Ο≤ΝΟΆΛρΛΡΛ·ΛλΛκΛοΛ±Λ«ΛœΛ ΛΛΛΈΛάΓΘ≤ώΦ“ΛΈΕΞΝηΆΞΑΧά≠Λ»ΛœΛ≥ΛΈ…’≤Ο≤ΝΟΆΛΈΝμΖΉΛ«ΛΔΛξ≤ώΦ“ΛΈΝμΈœάοΛ ΛΈΛάΓΘ
ΑλΓΥάΒΡΨΛΥΗάΛΠΛ»ΓΔάΈΛœΞόΞΥΞεΞΔΞκΛ§ΛΔΛόΛξΙΞΛ≠Λ«ΛœΛ Λ·ΓΔΩΆΛρΞόΞΥΞεΞΔΞκΛ««ϊΛκΛηΛΠΛ ΒΛΛ§ΛΖΛΤΓΔΤ…ΛύΛΈΛβΫώΛ·ΛΈΛβΛαΛσΛ…Λ·ΛΒΛΛΓΘΗΫΨλΛœάΗΛ≠ ΣΛάΛΖΓΔΨθΕΖΛΥ±ΰΛΗΛΤΈΉΒΓ±ΰ ―ΛΥΫάΤπΛ ¬–±ΰΛΙΛλΛ–ΛΛΛΛΛ»ΙΆΛ®ΛΤΛΛΛΩΓΘΛΛΛοΛφΛκΓ÷Έ…Λ≠ΛΥΖΉΛιΛΠΓΉΛάΓΘ
ΤσΓΥΛΖΛΪΛΖΓΔ≤ώΦ“Λ§Ψ·ΛΖΛΚΛΡά°ΡΙΛΖΛΤΛ≠ΛΤΓΔΩΆΩτΛβΝΐΛ®ΛΤΓΔΛΫΛΠΛβΗάΛΟΛΤΛιΛλΛ Λ·Λ ΛΟΛΩΓΘΦΪ §ΑλΩΆΛδΨ·ΩτΛ«ΛδΛΟΛΤΛΛΛΩΚΔΛΈΓ÷ΑΛ“ΏΛΈΗΤΒέΓΉΛδΓ÷Λ ΛσΛ»Λ Λ·≈ΝΛοΛκ¥ΕΛΗΓΉΛœΓΔΛόΛΟΛΩΛ·ΡΧΆ―ΛΖΛ Λ·Λ ΛξΓΔΛύΛΖΛμΓΔΛΫΛλΛ§ΗΕΑχΛ«ΞΏΞΙΛδΞ»ΞιΞ÷ΞκΛ§Β·Λ≠ΛΤΛΖΛόΛΠΛηΛΠΛΥΛ ΛΟΛΩΓΘ
ΜΑΓΥΛΫΛλΛρ≤ρΨΟΛΙΛκΛΩΛαΛΥΞόΞΥΞεΞΔΞκΛδΦξΫγΫώΛρΚνά°ΛΖΛΤΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΞΖΞΙΞΤΞύΛρΙΫΟέΛΖΛΤΘ…Θ”Θœ(ΙώΚίΒ§≥ )ΛρΦηΤάΛΖΛΩΛΈΛ§ΧσΘ≤ΘΑ«·ΝΑΓΘΛΫΛλΛœΟ·Λ§ΛΛΛΡΛδΛΟΛΤΛβΑλΡξΛΈ… ΦΝΛ§Ϋ–ΛκΛηΛΠΛΥΛΙΛκΛΩΛαΛΈΓ÷ΖΩΓΉΛδΓ÷ΞκΓΦΞκΓΉΛΏΛΩΛΛΛ ΛβΛΈΛ«ΓΔΛ≥ΛλΛ§ΛΔΛκΛΪΛ ΛΛΛΪΛ«ΗΫΨλΛΈΕέΡΞ¥ΕΛδΜ≈ΜωΛΈ¥πΫύΛ§¬γΛ≠Λ· ―ΛοΛΟΛΩΓΘ
ΜΆΓΥΚΘΛœΛΫΛΈΦηΤάΛΖΛΩΘ≥ΛΡΛΈΘ…Θ”ΘœΛ⬥ŻΛΖΛΤΙώΚί«ßΨΎΛœ ÷ΨεΛΖΛΩΛ§ΓΔΤ≥ΤΰΛΖΛΤΛΛΛκΞόΞΆΞΗΞαΞσΞ»ΞΖΞΙΞΤΞύΛœΖ―¬≥ΛΖΛΤ±ΩΆ―ΛΖΛΤΛΛΛκΓΘΗΫΚΏΛΫΛΈΞόΞΥΞεΞΔΞκΛδΦξΫγΫώΛβ…τΧγΥηΛΥΞξΞΥΞεΓΦΞΔΞκΛΥΦηΛξ≥ίΛΪΛΟΛΤΛΛΛκΓΘΛ≥ΛλΛόΛ«ΛΈΖ–Η≥ΛδΟΈΗΪΓΔΑ≈ΧέΟΈΛ Λ…ΛρΖΝΦΑΟΈ≤ΫΛΖΛΤΡ…≤ΟΛΙΛκΛΩΛαΛάΓΘ
ΗόΓΥΩΖΩΆΛ§ΤΰΛΟΛΤΛ≠ΛΩΛ»Λ≠ΛΥΓΔΕΒΛ®ΛκΩΆΛΈΖ–Η≥Λδ«ΫΈœΛΥΛηΛΟΛΤΞ–ΞιΞ–ΞιΛ άβΧάΛρΛΒΛλΛκΛ»ΓΔΕΒΛοΛκ¬ΠΛβΚ°ΆπΛΙΛκΓΘΛΖΛΪΛΖΓΔΞόΞΥΞεΞΔΞκΛ§ΛΖΛΟΛΪΛξάΑ»ςΛΒΛλΛΤΛΔΛλΛ–ΓΔΕΒΛ®Λκ ΐΛβΞ÷ΞλΛ ΛΛΛΖΓΔΕΒΛοΛκ ΐΛβΆΐ≤ρΛ§ΩΦΛόΛκΛΖΑ¬Ω¥Λ«Λ≠ΛκΓΘΗΫΨλΛ«»ΫΟ«ΛΥΧ¬ΛΟΛΩΛ»Λ≠ΛœΞόΞΥΞεΞΔΞκΛρΗΪΛλΛ–ΛΛΛΛΛΈΛάΓΘ
œΜΓΥΛβΛΝΛμΛσΓΔΞόΞΥΞεΞΔΞκΛ§άδ¬–ΛΗΛψΛ ΛΛΛΖΝ¥ΛΤΛΗΛψΛ ΛΛΓΘΜΰΛΥΛηΛΟΛΤΛœΗΫΨλΛ«ΝέΡξ≥ΑΛΈΛ≥Λ»Λ§Β·Λ≥ΛλΛ–ΓΔΩΉ¬°Λ«≈§άΎΛ »ΫΟ«Λ§ΒαΛαΛιΛλΛκΛ≥Λ»ΛβΛΔΛκΛΖΓ÷ΛΫΛΈΨλΛ«ΦΪ §Λ«ΙΆΛ®ΛΤΖηΛαΛκΈœΓΉΛβΑιΛΤΛΩΛΛΓΘΛΖΛΪΛΖΓΔΛΫΛλΛβ¥πΫύΛ§ΛΔΛκΛΪΛιΛ≥ΛΫΓΔ±ΰΆ―ΛβΛ«Λ≠ΛκΛΈΛάΛ»ΜΉΛΠΓΘ
ΦΖΓΥΞΆΞ§ΞΤΞΘΞ÷ΛΥΓ÷ΞόΞΥΞεΞΔΞκΛ§ΛΔΛκΛ»ΞμΞήΞΟΞ»ΛΏΛΩΛΛΛΥΛ ΛκΓΉΛ»ΛΪΓ÷Λ ΛσΛ«ΛβΛΪΛσΛ«ΛβΞόΞΥΞεΞΔΞκΡΧΛξΛΥΛΙΛλΛ–ΛΛΛΛΓΉΛ»ΗάΛΠΩΆΛβΛΛΛκΛ§ΓΔΜδΛœΒ’ΛάΛ»ΜΉΛΟΛΤΛκΓΘΞόΞΥΞεΞΔΞκΛ§ΛΔΛκΛΪΛιΛ≥ΛΫΓΔΛΏΛσΛ ΛΥΚέΈΧΛδΗΔΗ¬ΛρΑ―ΨυΛ«Λ≠ΛκΛΈΛάΓΘ¥πΥήΛΈΖΩΛ§ΛΔΛκΛΪΛιΓΔΑ¬Ω¥ΛΖΛΤΤΑΛ±ΛκΛΖΓΔΙ©…ΉΛβΛ«Λ≠Λκ
»§ΓΥΛΖΛΪΛβΖζάΏΕ»ΛΈΛηΛΠΛ ΨοΛΥΗΫΨλΛΈ¥ΡΕ≠ΛδΨθΕΖΛ§ ―≤ΫΛΙΛκΜ≈ΜωΛœΓ÷ΖηΛαΛΩΛ≥Λ»ΛρΓΔΖηΛαΛΩΡΧΛξΛΥΛδΛκΓΉΛ≥Λ»Λ§Αλ»÷ΛύΛΚΛΪΛΖΛΛΓΘΛΫΛΈΓ÷ΖηΛαΛΩΛ≥Λ»ΓΉΛρΗάΗλ≤ΫΛΖΛΤΓΔΟ·Λ«ΛβΚΤΗΫΛ«Λ≠ΛκΛηΛΠΛΥΛΙΛκΓΘΛΫΛλΛ§ΞόΞΥΞεΞΔΞκΛΈΥή≈ωΛΈΧρ≥δΛάΛ»ΜΉΛΟΛΤΛκΓΘΞόΞΥΞεΞΔΞκΛ§ΛΏΛσΛ ΛρΞξΞΙΞ·ΛΪΛιΦιΛΟΛΤΛ·ΛλΛκΛΈΛάΓΘ
ΕεΓΥ≤ΩΛΪΞ»ΞιΞ÷ΞκΛ§Β·Λ≠ΛΩΛ»Λ≠ΛβΓ÷ΞκΓΦΞκΛ…ΛΣΛξΛΥΛδΛΟΛΩΛΪΓΉΛ§≥Έ«ßΛ«Λ≠ΛκΓΘΞόΞΥΞεΞΔΞκΛ§ΛΔΛκΛάΛ±Λ«ΓΔΗΕΑχ §άœΛβΝαΛ·Λ ΛκΛΖΓΔΧΛΝ≥Υ…ΜΏΛδΚΤ»·Υ…ΜΏΛΥΛβΛΡΛ Λ§ΛκΓΘ¥Ε≥–Λ«ΛœΛ Λ·ΓΔΜ≈Ν»ΛΏΛ«ΦιΛκΓΘΦ“ΑςΛδ≤ώΦ“ΛρΦιΛκΛ»ΛœΓΔΛΫΛΠΛΛΛΠΛ≥Λ»ΛάΛ»ΜΉΛΠΓΘ
ΫΫΓΥΞόΞΥΞεΞΔΞκΛœΒγΕΰΛ«ΛΏΛσΛ Λρ«ϊΛκΛβΛΈΛ«ΛœΛ Λ·Γ÷ΦΓΛΥΛΡΛ ΛΑΛΩΛαΛΈΛβΛΈΓΉΓΘΩΠΩΆΛΈΒΜΫ―ΛβΓΔ±ΡΕ»ΛΈΞΈΞΠΞœΞΠΛβΓΔ¥…ΆΐΛΈΙ©…ΉΛβΓΔΝ¥…τΒ≠œΩΛΖΛΤά° Η≤ΫΛΖΛΤΖΝΦΑΟΈ≤ΫΛΖΛ ΛΛΛ»ΛβΛΟΛΩΛΛΛ ΛΛΓΘΛάΛΪΛιΞόΞΥΞεΞΔΞκΛœΈ©«…Λ ΟΈΚβΛ»ΛΖΛΤΨοΛΥΞΔΞΟΞΉΞ«ΓΦΞ»ΛΖΛΤΛΛΛΪΛ Λ±ΛλΛ–Λ ΛιΛ ΛΛΛΈΛάΓΘ
ΑλΓΥΚ«ΕαΓΔΩΆΛρΚΈΛκΛ≥Λ»ΛΥή΢ΞκΞ°ΓΦΛρΜ»ΛΟΛΤΛΛΛκΓΘΜήΙ©¥…ΆΐΓΔ±ΡΕ»ΓΔΩΠΩΆΓΔΜωΧ≥ΓΘΛ…ΛΈΩΠΦοΛβ¬≠ΛξΛΤΛΛΛ ΛΛΓΘΛΣ±ΔΆΆΛ«Ά≠ΤώΛΛΛ≥Λ»ΛΥΜ≈ΜωΛΈΑΆΆξΛœΝΐΛ®ΛΤΛΛΛκΛ§ΓΔΑλΫοΛΥΛδΛλΛκΟγ¥÷Λ§Ρ…ΛΛΛΡΛΛΛΤΛΛΛ ΛΛΓΘΛ≥ΛΈΛόΛόΛάΛ»ΓΔΞΝΞψΞσΞΙΛρΤ®ΛΙΛΪΓΔΚΘΛΈΞαΞσΞ–ΓΦΛΥ…ιΟ¥Λ§ΛΪΛΪΛκΓΘ
ΤσΓΥ≤ώΦ“Λρ¬γΛ≠Λ·ά°ΡΙΛΒΛΜΛκΛΩΛαΛΥΛœΓΔΓ÷ΛΛΛΛΩΆΓΉΛ»ΑλΫοΛΥΛδΛλΛκΛΪΛ…ΛΠΛΪΓΘ≤ΩΛρΛδΛκΛΪΓΔΛηΛξΛβΓΔΟ·Λ»ΛδΛκΛΪΓΘΩτΜζΛρΩ≠Λ–ΛΙΛηΛξΓΔΗΫΨλΛρΜΌΛ®ΛκΓ÷ΩΆΓΉΛρΛ…ΛΠΑιΛΤΛκΛΪΛΈ ΐΛ§ΓΔΛηΛΟΛίΛ…ΤώΛΖΛΛΛΖΓΔΛδΛξΛ§ΛΛΛβΛΔΛκΓΘ
ΜΑΓΥΚΘΛœΛ…ΛΈΕ»≥ΠΛβΤ±ΛΗΛάΛμΛΠΛ§ΓΔΖζάΏΕ»≥ΠΛβΈψ≥ΑΛ«ΛœΛ Λ·ΑΒ≈ί≈ΣΛΥΩΆΛ§¬≠ΛιΛ ΛΛΓΘΦψΛΛΩΆΛβΗΚΛΟΛΤΛΛΛκΓΘΞΛΞαΓΦΞΗΛβΘ≥ΘΥ(Λ≠ΛΡΛΛΓΠ±χΛΛΓΠ¥μΗ±)Λ»ΗάΛοΛλΛΤάΒΡΨΛΔΛόΛξΈ…Λ·Λ ΛΛΓΘΛάΛΪΛιΛ≥ΛΫΓΔΛ≥ΛΝΛιΛΪΛι βΛΏ¥σΛιΛ ΛΛΛ»ΛΛΛ±Λ ΛΛΛ»ΜΉΛΟΛΤΛΛΛκΓΘ¬‘ΛΟΛΤΛκΛάΛ±Λ«ΛœΟ·ΛβΆηΛΤΛ·ΛλΛ ΛΛΓΘ
ΜΆΓΥΛΠΛΝΛΈ≤ώΦ“ΛΥΛœΞΒΞΠΞ Λ§ΛΔΛκΓΔΟ¬άΗΤϋΛΥΞΉΞλΞΦΞσΞ»Λ§ΤœΛ·ΓΔΖνΑλΛΈΩ©Μω≤ώΛβ≤ώΦ“Λ§Ν¥≥έΫ–ΛΖΛΤΛ·ΛλΛκΓΔBBQΛδΨΤΡΜΓΔΞΩΞ≥Ξ―άΏ»ςΛβ¥ΑύζΓΔΞήΓΦΞξΞσΞΑ¬γ≤ώΛβΛΔΛκΓΘΑλΗΪΆΖΛσΛ«ΛκΛηΛΠΛΥΗΪΛ®ΛκΛΪΛβΛΖΛλΛ ΛΛΛ§ΓΔΦ“ΑςΛ§≥ΎΛΖΛΫΛΠΛΥΤ·ΛΛΛΤΛκ≤ώΦ“ΛΥΩΆΛ§ΫΗΛόΛκΓΘΜδΛβ≥ΎΛΖΛΛΓ Ψ–ΓΥΓΘ
ΗόΓΥΛΏΛσΛ Λ«ΑλΫοΛΥΙΆΛ®ΛΤΓΔΗΫΨλΛ«ΑλΫοΛΥ¥άΛρΛΪΛΛΛΤΓΔΟγ¥÷Λ»ΥήΒΛΥή≤ΜΛ«œΟΛΙΓΘΛΫΛσΛ ΥηΤϋΛΈΟφΛ«Γ÷Λ≥Λ≥ΛΥΤΰΛΟΛΤΛηΛΪΛΟΛΩΓΉΛ»ΜΉΛΟΛΤΛβΛιΛ®ΛΩΛιΓΔΛΫΛλΛ§Αλ»÷ΛΠΛλΛΖΛΛΓΘΛΝΛ ΛΏΛΥΛΠΛΝΛœΓΊΗήΒ“ΛρΜΌΛ®ΓΔΟγ¥÷ΛρΑΠΛΖΓΔΟœΑηΛρΦιΛμΛΠΓΌΛ»ΛΛΛΠPOLICYΛρΖ«Λ≤ΛΤΥηΡΪΨßœ¬ΛΖΛΤΛΛΛκΓΘ
œΜΓΥΩΆΛΈΚΈΆ―Λ»ΛΛΛΠΛΈΛœΓΔΖκΕ…ΛœΟγ¥÷ΫΗΛαΓΘΟ·ΛρΞ–ΞΙΛΥΨηΛΜΛκΛΪΛ»ΛΛΛΠΛ≥Λ»ΓΘΆζΈρΫώΛηΛξΓΔ≤ώΛΟΛΤœΟΛΖΛΩΛ»Λ≠ΛΈΕθΒΛ¥ΕΛρΩ°ΛΗΛΩΛΛΓΘΚ«ΗεΛœΞΙΞ≠ΞκΛηΛξΞΠΞΘΞκΛάΛ»ΜΉΛΠΓΘΓ÷Λ≥ΛΛΛΡΛ»ΑλΫοΛΥ±σΛ·ΛόΛ«Ι‘Λ±ΛκΛΪΓΉΛ»ΛΛΛΠ¥πΫύΛ«»ΫΟ«ΛΖΛΩ ΐΛ§ΛΠΛόΛ·ΛΛΛ·Λ≥Λ»Λ§¬ΩΛΛΒΛΛ§ΛΙΛκΓΘ
ΦΖΓΥΜήΙ©¥…ΆΐΛœΞœΓΦΞ…Λ Μ≈ΜωΓΘΡΪΛβΝαΛΛΛΖΓΔ±ΪΛβ…ςΛβΛΔΛκΓΘΞ»ΞιΞ÷ΞκΛβΛΔΛκΓΘΛ«ΛβΓΔΛΫΛλΛ«ΛβΓ÷ΛδΛΟΛΤΛηΛΪΛΟΛΩΓΉΛ»ΜΉΛ®ΛκΛΈΛ§ΓΔΛ≥ΛΈΜ≈ΜωΛΈΧΧ«ρΛΒΛάΛ»ΜΉΛΠΓΘΗΫΨλΛρΤΑΛΪΛΙά’«ΛΛ»ΗΊΛξΛ§ΛΔΛκΓΘΧΒΜωΛΥΙ©¥ϋΡΧΛξΛΥΙ©ΜωΛρ¥ΑΈΜΛΒΛΜΛΩΛ»Λ≠ΛΈΟΘά°¥ΕΛœ¥ΕΧΒΈΧΓΘ
»§ΓΥ±ΡΕ»ΛβΤ±ΛΗΛάΛ»ΜΉΛΠΓΘΙ©ΜωΛρΛ»ΛΟΛΤΛ·ΛκΛΈΛœΖηΛΖΛΤ¥ Ο±Λ«ΛœΛ ΛΛΓΘΒ§ΧœΛ§¬γΛ≠Λ·Λ ΛλΛ–Λ ΛκΛέΛ…ΕΞΙγΛβΝΐΛ®ΛκΛΖΤώΑΉ≈ΌΛβΨεΛ§ΛκΓΘΛΖΛΪΛΖΓΔΛΣΒ“ΆΆΛΪΛιΩ°ΆξΛΒΛλΛΤΓΔ»·ΟμΛρΡΚΛΛΛΩΛ»Λ≠Λœ≤Ω ΣΛΥΛβ¬εΛ®Λ§ΛΩΛΛΛ·ΛιΛΛ¥ρΛΖΛΛΓΘΛΫΛΠΛδΛΟΛΤΩΆΛ»ΩΆΛ»ΛΈΛΡΛ Λ§ΛξΛΈΟφΛ«ΓΔΖκ≤ΧΛ§ΛΡΛΛΛΤΛ·ΛκΓΘ
ΕεΓΥΛΠΛΝΛΥΕΫΧΘΛρΜΐΛΟΛΩΩΆΛœΓΔΛόΛΚ≤ώΦ“ΛρΗΪΛΥΆηΛΤΛέΛΖΛΛΓΘΧΧάήΛ»ΛΪΝΣΙΆΛ»ΛΪΛΗΛψΛ Λ·ΓΔΗΪ≥ΊΓΔΜκΜΓΛ»ΛΛΛΠΖΎΛΛ¥ΕΛΗΛ«ΛΛΛΛΓΘΗΫΨλΛβΦ“ΤβΛβΓΔΝ¥…τΗΪΛΤΛβΛιΛ®Λ–ΛΛΛΛΓΘ±ΘΛΙΛβΛΈΛœ≤ΩΛβΛ ΛΛΛΖΓΔΛύΛΖΛμΓΔΚΘΛΈΛΔΛξΛΈΛόΛόΛρΗΪΛΤΛέΛΖΛΛΓΘ
ΫΫΓΥΩΆΛ§ ―ΛοΛλΛ–≤ώΦ“Λ§ ―ΛοΛκΓΘ≤ώΦ“Λ§ ―ΛοΛλΛ–ΓΔΦ“≤ώΛ§Ψ·ΛΖΛάΛ±Έ…Λ·Λ ΛκΓΘΛΫΛΠΩ°ΛΗΛΤΓΔΚΘΤϋΛβΆζΈρΫώΛάΛ±ΛΗΛψΛ Λ·Γ÷ΩΆΓΉΛρΗΪΛΤΛΛΛ≠ΛΩΛΛΓΘΩΆάΗΛΈ¬γΜωΛ Μΰ¥÷ΛρΆ¬ΛΪΛκΑ ΨεΓΔΛ≥ΛΝΛιΛβ≥–ΗγΛρΜΐΛΟΛΤΩΩάΒΧΧΛΪΛιΗΰΛ≠ΙγΛΛΛΩΛΛΓΘ